- 「需要の価格弾力性」という言葉を聞きますが、どう理解すればよいでしょうか。また、実務上ではどのように活用すればよいでしょうか?(日雑メーカー・営業企画部、31歳)
-
一般的には,ある財の価格が上昇するとその財の需要量は減少します。従って、さまざまな価格における需要量を示す需要曲線(DD)は右下がりで示すことができます。「需要の価格弾力性」とは、価格を上げ下げする変化率に対し需要量がどれほど変化するかの比率を指したものです(図表1)。右下がりのため、需要の価格弾力性はマイナスの値になるため、絶対値が用いられます。
価格弾力性の一般的な見方を整理します。通常、価格弾力性の値が1を超えると弾力的であるといい、1未満の場合は非弾力的であるといった表現をします。これは、価格弾力性が1の場合は、価格の変動率と同じ水準で需要が変動することを示す(弾力性が均衡する)からです。価格弾力性と商品の性質の関係は、次のように整理できます。
- 価格弾力性が小さい(価格が変動しても、需要の変動は小さい)
生活必需品や代替性のある商品が存在しない商品や所得と比べ、支出額の小さい商品などに多くみられる - 価格弾力性が大きい(価格が変動すると、需要の変動も大きい)
贅沢品や代替性ある商品が存在する場合や所得と比べて支出額の大きい商品などに多くみられる
図表1.価格弾力性とその計算例
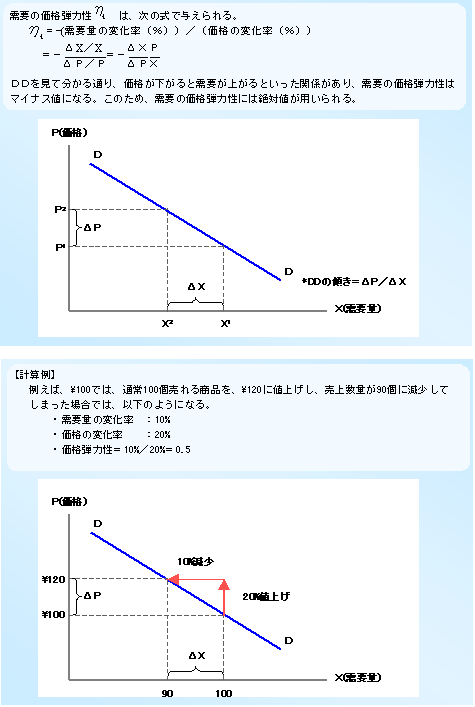
価格弾力性を実務に活用する視点を三つほどあげてみましょう。
1.価格設定の際に配慮する
例えば、リニューアル商品を市場投入する際、市場特性によって価格設定が変わってきます。仮に弾力性の小さい市場であればこれまでより高い価格設定ができる可能性があり、逆に弾力性の大きい市場では低価格設定を検討する必要も考えられます。価格弾力性だけで価格決定できるわけではありませんが、価格設定時の配慮点として活用します。
2.売価コントロールの基準とする
同様に、売価コントロールの基準として活用することができます。値下げ政策が効果的な商品は価格弾力性値が1より大きな商品です。逆に、弾力性値が1より小さい商品は(程度にもよりますが)値上げをしても需要減少の影響が少ない商品であると捉えることができます。デフレ経済であると言って、闇雲に値下げ政策を採るのではなく、価格弾力性を基準に入れて商品別の売価コントロール政策を検討すべきです。
3.小売との取り組みの材料に活用する
価格弾力性は、売価変更を伴う実販売を行った際の販売データがないと算出できません。メーカーであれば取引小売業との共同取り組みやPOSデータ分析などを通じ、価格弾力性を掴むことができます。このことは、小売との間で売価コントロールのための指標を共有する機会も生み出します。小売業は特売依存しがちです。しかし、価格弾力性を考慮しない特売では、売上が増えないばかりか値引きにより利益確保が難しくなるという問題も発生します。小売の売上と利益について議論する材料としてもこの価格弾力性データを活用することをおすすめします。
スーパーなどの既存店売上は前年割れが続いていますが、その要因は客単価下落によるものです。積極的な売価提案と店頭提案が求められています。
- 価格弾力性が小さい(価格が変動しても、需要の変動は小さい)
無料の会員登録をするだけで、
最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。
参照コンテンツ
- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 第107号 2019春の食品値上げラッシュ!値上げ方法で明暗
- MNEXT 消費の弱い時期の「安売り回帰」は正解か?(2016年)
- MNEXT 情報ディファレンスによる差別化-情報のマーケティング(2003年)
- JMRからの提案 不況下における価格・品質政策-成否の鍵を握る弾力性(2009年)
- JMRからの提案 価格差別化戦略 -利用チャネルをシグナルとした戦略的プライシング
- JMRからの提案 値上げの経済分析(2008年)
- ミクロ経済学入門
関連FAQ
関連用語
特集:2022年、値上げをどう乗り切るか
特集1.値上げの価格戦略
- MNEXT 眼のつけどころ 値上げの時代の生き残りマーケティング(2022年)
- MNEXT 眼のつけどころ 市場脱皮期の富裕層開拓マーケティング―価格差別化戦略(2021年)
- MNEXT 値上げをチャンスに変える(2008年)
- MNEXT 不況下でもうまい価格対応で伸びる企業(2009年)
- 戦略ケース 値上げと小売業の競争 物価上昇で小売とメーカーは新競争時代に突入(2022年)
- 戦略ケース 値上げの現場 花王―戦略的値上げで収益性向上なるか(2022年)
- 戦略ケース 利益率低下により再値上げに踏み切ったキユーピー(2008年)
- 戦略ケース 値上げか値下げか-消費低迷下の価格戦略(2008年)
- マーケティングFAQ 「需要の価格弾力性」とは
特集2.値上げが企業の収益に与えるインパクトを分析
特集3.消費者は値上げをどう受け止めたのか?
- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 2019春の食品値上げラッシュ!値上げ方法で明暗(2019年)
- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 値上げの影響を受けやすい牛乳、受けにくいマヨネーズ(2013年)
- 「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 食品の値上げと安全性(2008年)
- MNEXT 下がる給料、増える生活費(2008年)
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー
コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




