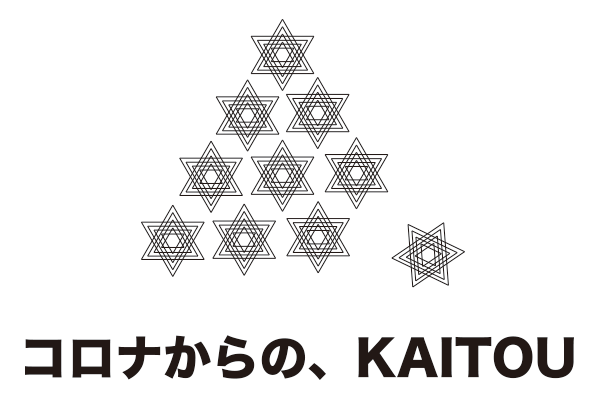
コロナによる食生活の変化などから、食の経験財化が進んでいます。それに対応するためには、ブランドの効果や購買行動の変化、チャネル選択などを考慮した価値拡張のマーケティングが必要になります。
まず価値の上がる場所として、パンを事例に説明したいと思います。この場合、場所というのは空間的な場所だけでなく、シーンなど広い概念でとらえています。
パンを食べる場所について、当社が毎年発刊している「消費社会白書」最新号の調査結果をみてみると、82%の人が自宅となっています。しかし、食べた場所によって、満足度に大きな違いが出ていることがわかりました。
例えば、レストランやホテルでパンを食べた場合は満足度が高く、自宅やオフィスで食べた場合は低くなっています。さらに、場所別のパンを食べた食事の支払金額と、どれくらいお金を払ってもいいかということを聞いてみると、職場やオフィスでパンを食べた食事をした場合に支払ってもいい金額は548円でした。一方、ホテルでパンを含めた食事をする場合は5,200円、レストランでは6,300円です。つまり、職場や自宅で食べるパンの食事よりも10倍程度に価値が高くなっています。

なぜこのような価値の差が生まれるかというと、レストランの方が丁寧に作られているとか、贅沢な感じがする、一緒に食べた人と楽しい時間が過ごせたという理由が挙がりました。また、パンと一緒に食べた料理も、自宅だと1.8品ですが、レストランでは2.5品でした。パンだけではなく、パンを含めた食事やその空間が価値を上げているということができます。
パンが、それを食べた場所によって価値が変わり、カフェやホテルで食べるパンは、他の商品と一緒に食べる補完財になります。さらにそれが外食などのサービスと結びつき、情報が付与されることで情報財化します。それが価値の高まる場所やシーンで経験されることで、経験財化していきます。この過程で、パンの価値はどんどん上がっていきます。
経験財化していく事例のひとつとして、「イータリー」という業態を紹介したいと思います。2002年にファリネッティという人のアイデアから生まれたものです。イタリアの高品質の食材を、伝統的な食文化と一緒に楽しんでもらうというコンセプトです。買う、食べる、学ぶが一緒にできるというのが特徴です。
世界で40店舗以上、日本では5店舗が展開されています。ですが、日本ではそれほどうまくいっているようには見えません。その理由のひとつが、扱う商品を経験財化できていないという点を挙げることができます。
本場イタリアの店舗では、店舗が真ん中にあり、その横に生鮮食品などの売場があります。まさに市場という雰囲気で、日本でいう築地の場外市場のようです。食材を買って、目の前で調理して食べる。そういう経験的な楽しみ方を提供しています。
一方、日本では生鮮食品はあまり置かれておらず、総菜を買って店舗で食べるといったイートイン的な雰囲気が強いです。イタリアの店舗のように経験財化できていないというのが課題といえそうです。
食生活の手作り志向、食の経験財化が進む中で、消費者は多くの情報に触れることになります。そのため、その情報を処理する負荷が非常に大きくなってきています。その負荷を軽減してくれるカギが、ブランドです。
ビールを例に挙げて、説明したいと思います。「消費社会白書2022」の調査では、ビールのブランドを重視していると答えた人が65%でした。また、ブランドによってビールを選ぶ理由として、「知っているブランドだと安心感がある」「知っているブランドなら新商品でも使い勝手が想像できる」「ブランドの品質の良し悪しをある程度判断できる」などが挙がりました。

ビール以外にも、アイスクリームやスマートフォンについて、スペックの評価とブランドの好意度の相関関係を出しました。スマホのGalaxyやXperia、ビールのキリン一番搾り、サントリーのザ・プレミアム・モルツは、スペックと好意度に強い相関がありました。
一方で、スペックと好意が強い相関にならないブランドもあります。例えば、アップルのiPhone、アサヒスーパードライ、アイスクリームのハーゲンダッツなどです。これらのブランドは、スペック以上に好意が形成されています。

この背景には、人間が持っている心理特性が働いているといえます。単純にスペックを合計して、それが高ければ好意に結びつき、購入に繋がるわけではありません。
ブランドの選択方法として、品質だけで選ぶと答えた人は35%でした。品質に加え、心理的特性で選ぶ人は30%でした。この心理特性のひとつに、ザイオンス効果があります。これは、なじみがある、知っている、そういう気持ちが好きに繋がるというものです。ふたつ目は、ヒューリスティックスです。富裕層が利用していたり、勢いのあるブランドだったり、モンドセレクションを受賞しているなど。そういうものが判断の近道になっていくというものです。もうひとつが、損失回避です。人は、お得な買物をするよりも損をする方が嫌だと感じます。そういった損失を回避するように行動します。
こういった人間の心理特性を発見して、それに対応することが重要なポイントになります。
「消費社会白書2026」のご案内

長く停滞していた日本の消費が、いま再び経済成長の牽引役として動き始めている。ようやく日本の消費は、「もはやバブル後ではない」と言える新たな局面に入った。
参照コンテンツ
- MNEXT 2022年の消費の読み方-価値拡張マーケティング(2021年)
- JMRからの提案 コロナからの、KAITOU ターゲットスライド、40代女性、食生活(2021年)
- MNEXT 凍結した消費マインドを溶解させるマーケティング―解除後の消費増加シナリオ(2021年)
- MNEXT 静かに激変する「当たり前の日常」と解凍消費(2021年)
- JMRからの提案 「消費社会白書2022」のふたつのアナザーストーリー(2021年)
- 「食と生活」のマンスリーニュースレター
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




