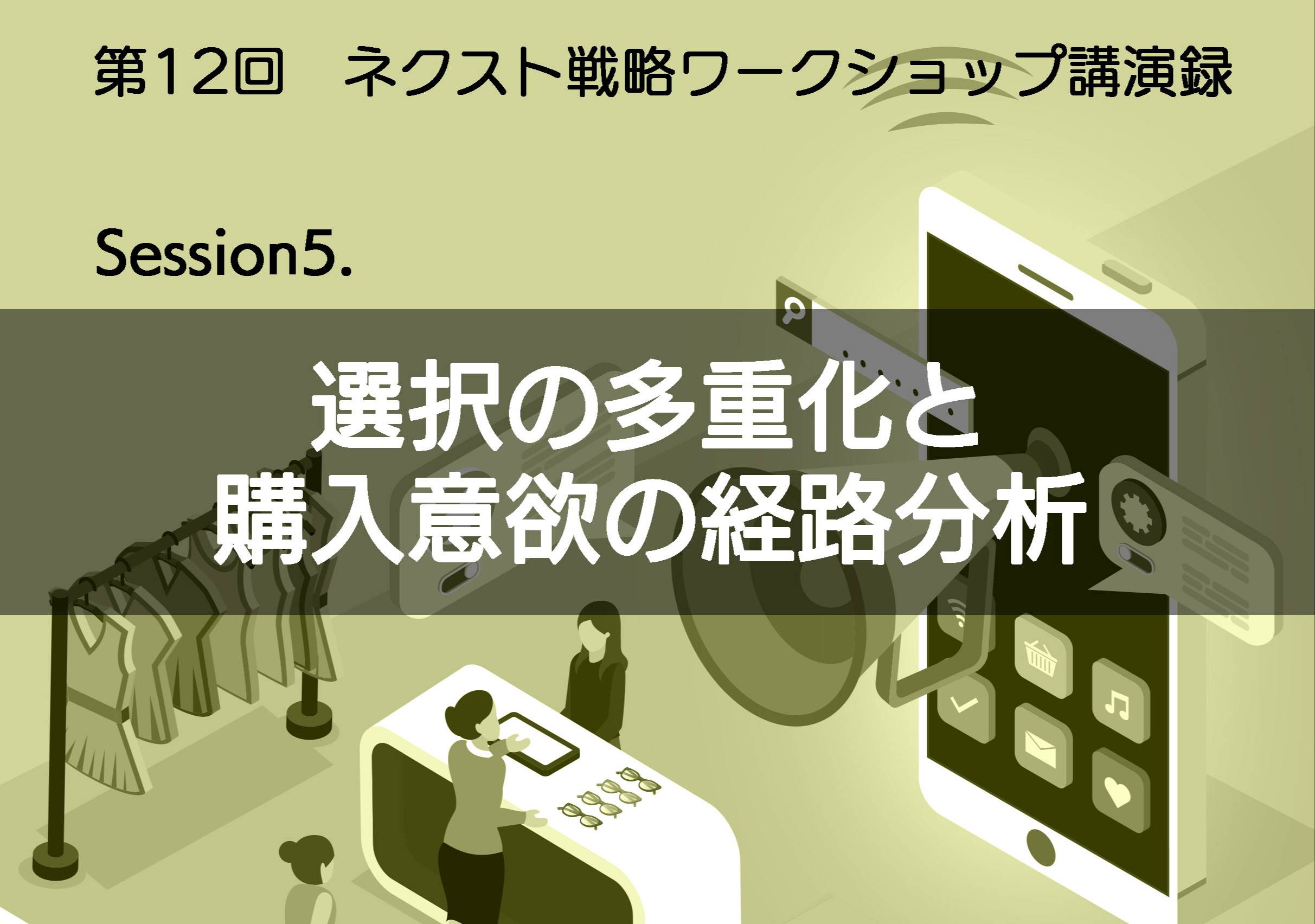
どのようにチャネル設計をして、どう商品を店頭で売っていくか。消費者の購買意欲をどう作っていくか。今、こういった経路を考えていくことが非常に重要です。消費社会白書2019の調査では、オンライン店舗と実店舗の使い分け、食品の購入チャネル、インターネットを使ったキャンペーンの効果などについても詳しく分析しました。
まず、商品ごとの購入先について見てみます。食品購入のメジャーチャネルは、「食品スーパー」「コンビニエンスストア」「大型総合スーパー」です。そこに、四つ目のチャネルとして「ドラッグストア」が台頭してきています。
図表1.購入先選択 ―食品購入四つのメジャーチャネル
ドラッグストアの1年内利用率は、38.8%でした。特に注目したいのは、居住地域別の利用率に差がある点です。利用率のトップは北関東で47.5%、東京都(23区内)は28.7%と最も低かったです。
図表2.ドラッグストアの食品売上シェア
ではドラッグストアでは実際、なにが買われているのでしょうか。食品スーパーと比べてみると、野菜・果物はスーパーの割合が圧倒的です。一方で、菓子、飲料や酒類などでは、その差が2割を切っています。
また、コンビニとの比較では、牛乳などの乳製品、調味料、卵などはドラッグストアで買われる方が多いです。お菓子や缶詰などは差がかなり小さいです。コンビニとドラッグストアは競争が激しいということが言えると思います。実際、地方で両店が並んで出店した場合、コンビニがドラッグストアに客を取られてしまうということもあるそうです。
図表3.ドラッグストアでの食品購入の優位性
このように、都市部で重点にすべきチャネルと、地方で重点にすべきチャネルは違っているということがデータから分かると思います。そもそも、ドラッグストアとそれ以外のチャネルでは、儲けを出す構造が違います。例えば、スーパーの売場で一番お金がかかるのは生鮮食品です。人手も必要で、廃棄ロスもあります。そのため、あまり儲からない売り場でもあります。一方、缶詰やお菓子などは利益の高い商品です。陳列すれば、あまり手のかからない売場だからです。しかし、この利益を生み出している商品がドラッグストアに奪われつつあります。
ドラッグストアの市場規模は7兆円といわれています。スーパーよりも販管費が低く、従業員も少なめです。人手がないので、商品を陳列して安く売るという戦略です。一方のスーパーは、人手が多いので、コストがかかりますが、旬や季節の提案、クロス陳列などもやってもらいやすいです。
「消費社会白書2026」のご案内

長く停滞していた日本の消費が、いま再び経済成長の牽引役として動き始めている。ようやく日本の消費は、「もはやバブル後ではない」と言える新たな局面に入った。
第12回 ネクスト戦略ワークショップ 講演録
- Session1. 情報的マーケティングへの革新
- Session2. ストイックな規律互助の価値観と消費見通し どうなる?これからの価値観と消費
- Session3. 食生活の理想と現実の乖離
- Session4. ロングセラーブランドの長寿化
- Session5. 選択の多重化と購入意欲の経路分析
参照コンテンツ
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




