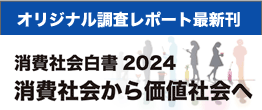林和夫

2023年3月のWBC(ワールドベースボール・クラシック)が大きな話題となっている。特に今回は大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)を筆頭に、メジャーリーグ所属の日本人選手ほぼ全員が参加を表明したこと、さらに米国も大谷の同僚マイク・トラウト選手をキャプテンに据えるなど「遂に本気を出した」点も大いに注目度を高めた。高額な入場券は完売し、NHK始め主力TV局がトップニュースで選手の一挙手一投足を追いかける。サッカーのカタールWorld Cupを超える興奮が期待されているのであろう。
2006年の第一回大会では、ICHIRO選手の活躍に引っ張られ、日本が待望の世界一に輝く。サッカー日本代表の台頭などにより、人気にやや陰りの見られたプロ野球が、再び輝きを取り戻す貴重な契機となった事は記憶に新しい。
さて、この頃からふと疑問を抱いたものである。「なぜ、野球という同じスポーツを競技しているのに、MLBに移籍した日本の選手がNPBの数倍にも及ぶ20億円を超える年俸を獲得できるのだろうか?」
参考文献
「消費社会白書2024」のご案内
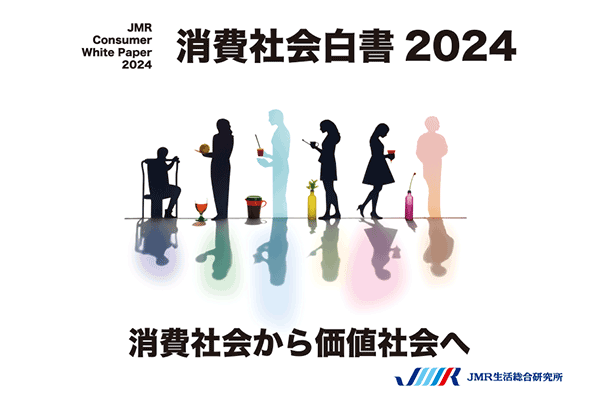
中流層の暮らしぶりは終わった。まん中がなくなって、焼け野原のような空洞感が支配している。「こころの戦後」だ。 「欲望自由主義」のもとで「個人欲望」の解放を可能にした消費社会は終わり、生きがいを求めてさまよう価値社会が始まった。
著者プロフィール
林和夫
1980年早稲田大学理工学部卒業後、電通に入社。25年間、FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、世界陸上、世界水泳など国際スポーツのスポンサーシップ、TV放映権、大会運営業務に携わる。97年からスイスのISL(電通とアディダスのスポーツビジネス会社)、2010年からは電通スポーツ(ロンドン)での勤務など国際経験を蓄積。2018年より広島経済大学にてスポーツビジネスを担当し、今日に至る。
参照コンテンツ
- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~なぜMLBとNPBで7倍の年俸格差があるのか?~ 第二話「MLBの成長を支えた経営戦略とは」(2023年)
- プロの視点 プロスポーツのマネジメント~広島東洋カープの挑戦~広島市と共に逆境を乗り越える独自の経営戦略(2022年)
- プロの視点 今治.夢スポーツ 「スポーツが日本の未来にできること」を求めて、岡田武史氏の挑戦(2021年)
- MNEXT 眼のつけどころ 戦略思考をどう身につけるか-スポーツ観戦で学ぶ(2019年)
- MNEXT 2014年ブラジルW杯観戦で学ぶ 実践戦略思考(2014年)
- MNEXT W杯のコートジボワール戦敗北の戦略的読み方(2014年)
- MNEXT W杯日本代表のリーグ戦敗退の戦略的読み方(2014年)
- MNEXT 北京五輪にみる日本の戦略の弱さ(2008年)
おすすめ新着記事

消費者調査データ 炭酸飲料(2024年7月版) 首位「コカ・コーラ」、迫る「三ツ矢サイダー」、高い再購入意向の無糖炭酸水
2023年は3年連続プラスとなった炭酸飲料。調査結果を見ると、今回も「コカ・コーラ」が複数項目で首位を獲得したが、2位の「三ツ矢サイダー」の猛追が光る。再購入意向は、無糖炭酸が上位に食い込んだ。

消費者調査データ スポーツドリンク・熱中症対策飲料(2024年7月版) 首位「ポカリスエット」、追い上げる「アクエリアス」
人流の回復や猛暑などを背景に伸びる熱中症対策飲料・スポーツドリンクの調査結果をみると、ロングセラー「ポカリスエット」が再購入意向を除く5項目で首位を獲得した。5ポイント程度の差で追うのは「アクエリアス」。さらに10ポイント前後のビハインドで「GREEN DA・KA・RA」が続く。

成長市場を探せ 初の6,000億円超え、猛暑に伸びるアイスクリーム
2023年度、空前の暑さを追い風に、アイスクリーム市場は初の6,000億円超えを達成、4年連続で過去最高を更新した。2023年の夏日日数は140日、実に1年の4割近くの日が「アイスクリームを食べたくなる」気温である25度を超えたことになる。










![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)