林和夫
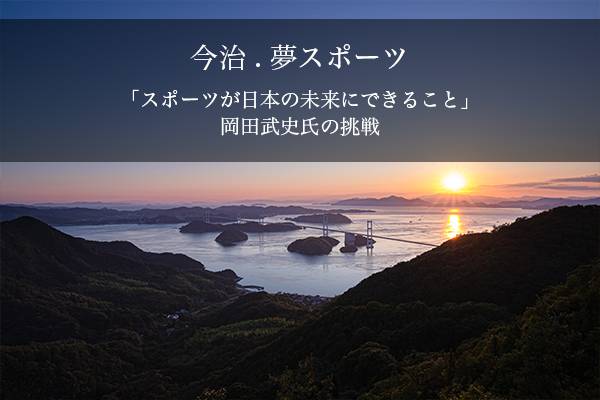
2度に渡ってサッカー日本男子代表監督を務めた岡田武史氏。その岡田氏が、2014年に「株式会社 今治.夢スポーツ」の株式51%を取得、オーナーとなった。「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」を企業理念に掲げる同社は、サッカーJ3のFC今治の運営を中心に、教育事業や地域貢献活動などさまざまな事業を手がけている。
代表監督の後、日本サッカー協会の副会長にも就任した岡田氏は、言うまでもなく日本サッカー界の重鎮だ。この転身はNHKを始め多数のメディアが伝え、多くの人に驚きと関心をもって受け止められた。
筆者は2020年に2度今治を訪れ、J3に昇格したFC今治の試合、環境プロジェクト運営など、今治.夢スポーツの具体的な活動を視察。岡田代表と関係者の方々から直接、話をうかがう機会を得た。その構想は驚くほど壮大だ。当コラムでは、その一端を紹介したい。

参考文献
著者プロフィール
林和夫
1980年早稲田大学理工学部卒業後、電通に入社。25年間、FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、世界陸上、世界水泳など国際スポーツのスポンサーシップ、TV放映権、大会運営業務に携わる。97年からスイスのISL(電通とアディダスのスポーツビジネス会社)、2010年からは電通スポーツ(ロンドン)での勤務など国際経験を蓄積。2018年より広島経済大学にてスポーツビジネスを担当し、今日に至る。
参照コンテンツ
- MNEXT 眼のつけどころ 戦略思考をどう身につけるか-スポーツ観戦で学ぶ(2019年)
- MNEXT 2014年ブラジルW杯観戦で学ぶ 実践戦略思考(2014年)
- MNEXT W杯のコートジボワール戦敗北の戦略的読み方(2014年)
- MNEXT W杯日本代表のリーグ戦敗退の戦略的読み方(2014年)
- MNEXT 北京五輪にみる日本の戦略の弱さ(2008年)
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




