- カテゴリーマネジメントという言葉をよく聞くのですが、どういうものですか?また具体的にすすめるにはどうしたらよいですか?
-
カテゴリーマネジメント(以下CM)とは、ブライアン・ハリスが提唱した概念で、その定義は
- 「カテゴリーマネジメントとは、カテゴリーを戦略的ビジネス単位として管理していくことであり、消費者に価値を提供することに集中することによって、業績を改善していくこと」
となっています。要は、小売業とメーカー(卸)が共同して、特定カテゴリーの収益を最大化するように取り組んでいこうとするものです。
具体的なすすめ方として、つぎのようなステップが提案されています(図表1)。
- 前提条件の統一(関与者の意思統一)
- カテゴリーの環境把握
- パートナー選定と目標値の設定
- 店頭展開
図表1 カテゴリーマネジメントの展開ステップ
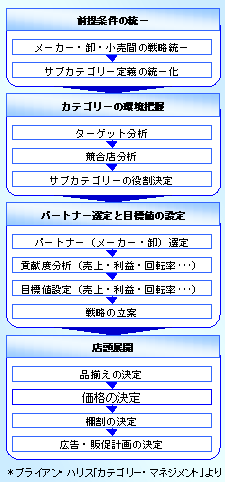
しかし、実際はうまくいっているケースは少ないといわれています(アメリカでは取り組んだ企業の60%が失敗、挫折したという報告もある)。
多くの企業でCMが標榜されていますが、現実には、つぎのようなケースが多くなっています。
- 春秋の定番棚割の見直しにしか活用されていない
- 売上の半数を占める定番外売場での展開は別ルールで実施される傾向が強い
- 結果として、定番棚割は崩壊し、カテゴリー全体でみると、生産性が低く差別性のない売場になってしまっている
そんななかで自社なりのCMを確立しようとしている企業もみられます。例えば、味の素は、定番棚割の活性化を目指した「カテマス」とクロスマーチャンダイジングによる定番外売場づくりを提案する「マックス」というふたつの武器を営業活動に活かそうとしています。
また、菱食では、自社なりのCMの体系を整理し、小売業とのカテゴリー一括取引を推進しています(図表2)。
ただし、実際には、小売企業独自のマネジメントスタイルにあわせることも重要です。例えばイトーヨーカ堂のような単品管理を徹底している企業には、CM提案は受け入れられないでしょう。また、イオンでは、「ベーシック」「ニューベーシック」「トレンド」というサブカテゴリーがあるのでそれを前提にしなければならない、など個別対応が必要とされている場合もあります。
図表2 菱食の提案するカテゴリーマネジメント
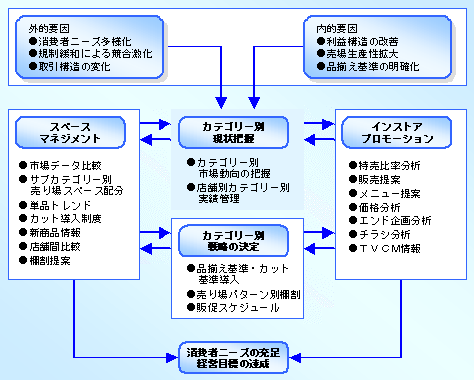
当社なりにポイントを整理すると、つぎの3点に集約できます。
- サブカテゴリーをどう定義するか
- どのような育成プランをつくるか(少なくとも半年の販促計画が必要)
- 仮説検証の仕組みがつくれるか
問題は、明確なカテゴリー戦略がメーカーと小売企業との間で共有されていないことに尽きます。とくにサブカテゴリーをどう形成し育成するかの視点と継続的な取り組みが弱いということが指摘できます。
無料の会員登録をするだけで、
最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。
関連用語
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー
コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




