小売市場の商圏間格差、企業間格差がひろがっている。メーカー営業は今、いかに魅力度の高い商業集積で勝つか、いかに有力小売企業で勝つかの戦いになっている。では、どんな商圏や企業に注目できるのか。躍進する小売企業をてがかりに、いくつかの営業のヒントを探ってみたい。
2001年度専門店調査によれば、日本の専門店の売上高ランキングは、ヤマダ電機が首位となり、次いでコジマ、ヨドバシカメラのような家電、カメラ専門量販店がトップ3を占めた。1991年ランキングと比べると、チヨダ・マルトミ(靴)、ダイクマ(DS)、青山商事(紳士服)など7社が脱落し、新たにヤマダ電機・コジマ(家電専門量販店)、ヨドバシカメラ・ビックカメラ(都市カメラ量販)、しまむら・大創産業のような低価格を売りにしながらも品揃えに趣向を凝らした企業がランクインしている。
これらの結果から次のようなチャンスを見いだすことができる。
図表.1991年度・2001年度専門店調査売上高ランキング
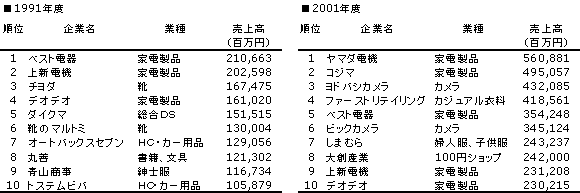
(1)都市のマーケット
ヨドバシカメラ、ビックカメラはともに都市の繁華街に大型店舗を構えることで成功している。ヨドバシカメラは新宿・大阪の梅田など都市への集中出店によって圧倒的な坪効率で成長を続けている。ビックカメラも池袋や新宿で百貨店との融合店舗で多くを集客している。最近では、ベスト電器が新宿高島屋内に出店して成果をあげている。ヤマダ電機も都市への出店を増やしている。都市の集客力が高まりマーケットとしての魅力度が高まっている。
(2)ニュースタイルマーケット
しまむらは婦人服、子供服のチェーンで、主に低価格路線で成功した企業であるが、最近では、海外視察によっていちはやく流行のファッション情報を仕入れ、メーカー・卸と共同で商品を開発し、短いサイクルで低コストで販売して利益を上げる仕組みによって成長している。新しいファッションや流行に目をつけ店頭に並べるスピードは伊勢丹新宿店より1ヶ月早いとも言われている。
(3)ワンプライスレジャーマーケット
大創産業(100円ショップのダイソー)の年間販売点数は20億点に及ぶ。国民1人当たりにすると年間16個になる。品揃えは6万点。毎月700点が加わっている。米国にもワンコイン販売方式の「ダラーゼネラル」等があるが、低所得者層の生活必需品ニーズに対応した品揃えになっている。一方、ダイソーの提供するのは「新しい買い物の楽しさ」であり、文具、アクセサリー、衣料など多様な品揃えから「主婦のレジャーランド」とも言われている。
都市の商圏で勝つこと、新しいスタイルをいちはやく取り込んだ店頭提案や、買い物を楽しくする仕掛けづくりに意欲のある店に注力すること、等が成果をあげるひとつのてがかりになるのではないだろうか。一方、こうした成功企業の売り方アイデアを自分なりに加工して提案の中に盛り込んでいくことも大切である。様々な成功企業に目を向けてみて欲しい。
参照コンテンツ
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




