- 最近の商談では、値引きやマージン要求がきつくなっているのですが、値下げを回避する方法はあるのでしょうか?
-
はじめに、小売業がなぜ値引き要求をするのかを考えてみましょう。その理由は、売上が伸びないからであり、売上を伸ばすには価格プロモーションしかないと安易に特売などで解決しようとするからです。
売上が伸びない理由を分析してみると、客数は横ばい、客単価が減少という構造になっていることが多いです。客単価の減少の背景には、1品当たり単価、1人当たり購入点数の双方が減少していることがあります。
値下げ要求を回避するには、客単価減少に歯止めをかけることです。まずは、1人当たり購入点数アップを狙った提案をすることが必要です。店頭販促提案には、一般的には次の四つのタイプがあります(図表1)。
- 単品大量陳列型
- カテゴリーフェア
- メーカー・ブランドフェア
- 生活提案
図表1 店頭販促提案のタイプ
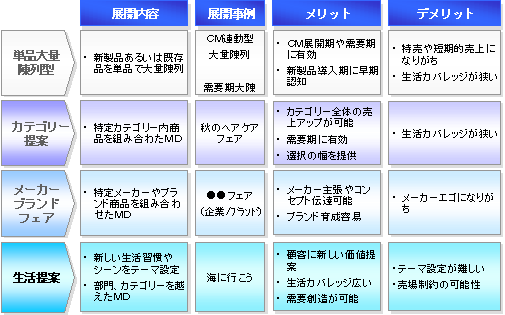
店頭提案をするわれわれも、多くの場合、単品大量陳列型が主流になっています。この場合、よほどの商品力やマーケティング投資がない限り、値引きに頼らざるを得ないのが現状です。値下げ回避の第一歩は、単品型企画からの脱却です。少なくともカテゴリーフェアを企画提案していくことが必要です。これにより、生活者への提案力が高まると同時に、購入点数アップが期待できます。
第二の方法は、1品単価を少しでも向上させることです。先進的なメーカーはすでに売価提案を積極的にすすめています。三つの切り口が考えられます。
ひとつは値引き幅を縮小させること。小売業は値引き価格の幅を複数パターン持っています。これをPOSデータで分析すると、値引き幅の違いほど販売数量・金額に大きな影響を与えないことが多いのです。過剰に値引きしている可能性があるのです。
ふたつめは、特長のあるマーチャンダイジングを提案すること。競合店にはない独自のサブカテゴリーの重点販促提案やさきほどの店頭提案タイプでいえば生活提案型の売場づくりを提案することです。これにより競合店との売価を気にする度合いを少なくしていくことです。そのためには、常に競合店の店頭観察なども必要になってきます。
三つめは、ある特定のアイテムの値引きは仕方がない、と割り切ってカテゴリーフェアなどの複数アイテム陳列やクロスマーチャンダイジングを展開することです。目玉となるアイテムで売場への立ち寄り率を高めながら、他ブランドや関連アイテムの購入促進をすすめるものです。
図表2 売価提案の可能性
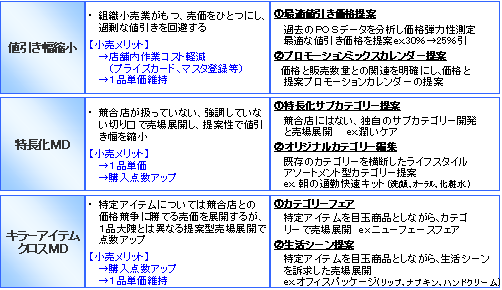
価格は最大のプロモーション手段であることは間違いありませんが、使う機会をよく検討しないといけません。売場提案も価格訴求型と提案型をミックスさせた店頭販促カレンダーの提案が求められます。
参照コンテンツ
関連用語
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー
コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




