消費財メーカーの営業マンが個店で行う活動は、商品取り扱い促進(特に本部契約の定番以外の歯抜けアイテムの導入や定番登録商品の各店導入)、売れる状態づくり(棚割り確保の上で優位置取りやフェイス増)、店頭販促の実施、新規店での売場確保などが主な目的である。特に店頭販促では、誰を対象とするか(消費者か売場の販売関与者か)、場所(常設の定番棚や関連棚か、エンドや平台か、特設コーナーか)、手段(セット・クロスMD、POP、サンプリング、マネキンデモ、大陳など)の組み合わせで検討することが求められてくる。
本社から送られてくる売場ツールは、その活用方法に関する指示が添付されており、ブランドマネージャーら戦略スタッフが営業を支援するために構築した戦略シナリオに準じている。営業マンは、基本的にはこの施策の意図を汲み取り、全社のブランド戦略推進のために機能することになるが、販売の現場である売場にはそのままのプランでは導入が困難である場合も少なくない。POPを取り付けるスペースが無い、メーカー名が印刷されているポスターは掲示できない、デモ販売員派遣を急に要請された、などである。
しかし、自社の計画と個店の条件が合わないからと言って施策展開を中止するわけにはいかないため、営業マンには現場での臨機応変な対応が求められる。そこで、目的と活用するツール類の関係を正しく捉えておく必要があるわけだが、主要な目的とツールの関係を整理してみよう。
売場を通じて達成させたい事項は、大別すると、商品の視認率を上げる、商品特徴を正しく伝達する、価格を告知する、新発売であることを伝える、商品の使い方を提案する、特別な売り出しであることを知らせる、特典付きなどを知らせる、売場の演出を高める、ブランドのイメージアップを図る、そして、個店とのパートナーシップを強くするなどの10項目を検討してみた。そして、その目的に対して活用できるツール類をツール類の持つ特徴からまとめてみた(図表)。
ポイントは、ツールは万能なものはなく、目的に対する期待効果によって使うものが決まってくるといった目的手段関係があるということである。何でもかんでもPOPを取付け、サンプリングをすれば良いということでないことに注意したい。そして、このように考えておけば、本社の戦略スタッフの想定外の条件を持つ売場が出てきた場合でも、目的を理解し、それに合う最適なツールを選択し、臨機応変に提案することができるはずだ。
図表.販促目的とツール・施策
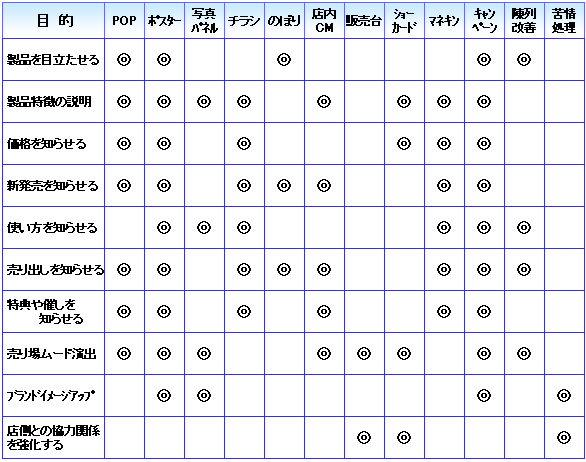
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




