長引く消費低迷により、業績悪化に苦しむ外食産業の中で、トップの日本マクドナルドは競合の追随を許さない高成長を続けている。1998年度12月期決算では、「全国2,852店・売上高3,779億円」を記録した。1971年の日本進出以来27期連続の増収である。業界2位のほっかほっか亭で1,726億円であり、2倍以上引き離すダントツのトップ企業である。
日本マクドナルドの戦略といえば、近年のハンバーガー市場を席巻している「低価格戦略」があげられるが、それとともに着目すべきは「エリア戦略」である。1993年に1,000店を超えてから年間100店以上の出店を継続し、1995年には当初の出店目標であった「商圏10万人に1店」をクリアした。と同時に「2010年・総店舗数10,000店・売上1兆円」という新たな出店目標を打ち出した。基本戦略は、「外食マーケットのシェア5%奪取」である。
1971年の第1号店出店から1980年代にかけては、多少の波こそあれ年間店舗増加は、平均で50店弱に過ぎなかった。それが1990年代に入り、新規出店攻勢に転じる。次第に出店ペースを上げ、1994年には137店と100店を超え、1995年は323店と前年比約2.5倍を記録した。そして、1996年は530店の出店である。
1996年をピークとして、そのペースは落ちてきているが、それでも1999年も新規出店見込みは400店。総店舗数は3,000店を超えることになる。創業から1,000店まで22年かかったが、3,000店まではわずか6年の短さである。
こうした、1990年代の新規出店攻勢には三つの要因があげられる。
図表1.売上高と店舗数の推移

図表2.年間店舗増加数と1店舗当たり売上の推移

(1)地価の下落
外的な要因としては、バブル後の地価の急激な下落があげられる。これまで慎重であった都市圏の生活沿線沿いへの出店、土日の売上を稼げないということで見送ってきたビジネス街といった空白エリアへの出店障壁を低くした。前者では、山手線主要ターミナルを基点とする東急・小田急・京王・東武・西武といった私鉄の駅前商店街。後者で山手線内のビジネス街であっても土日でもイベントなどで集客が見込めそうなエリアへの出店である。例えば、多種のイベントが開催される日本武道館のある九段下などがこれに該当する。
(2)多様な店舗フォーマット
地価の下落もさることながら出店フォーマットの多様化が新規出店をより加速させた。
これまでは、「店舗面積70坪以上・年商2~3億円」がひとつの新規出店基準であり、この条件を満たすエリアへの出店を原則としていた。これでは必然的に都市圏の主要ターミナルや郊外主要幹線沿い(ドライブスルー)、地方圏の大型商業集積に出店の選択肢が限定されていた。現在は、店舗面積に応じて5タイプの店舗フォーマットが展開されている。立地に合わせ、店舗面積15坪の小型店から70坪以上の大型店まで、売上年商5,000万円から2、3億円までと多様なフォーマットを展開している。
(3)異業種との新型店舗開発
単独店として新規出店を進める一方で、日本石油をはじめとするガソリンスタンドやCVSとの共同による新型店舗の開発も積極的に進めてきた。近年は規制緩和の流れの中で展開が始まった「セルフガソリンスタンド」との併設店の開発が試行されている。
一番のメリットは出店コストの低さである。
従来型の「商店街」という形態の形骸化が進む中、単独で集客を図るよりもお互いのメリットを追求するということで、今後はこうした異業種との新型店舗開発が急ピッチで進められていくと思われる。
1990年代の新規出店攻勢の背景には、直近の競合となるファストフードチェーンやファミリーレストラン、加えてCVSや宅配といった新規の食提供業態の台頭がある。エリアの胃袋シェア獲得競争が激化する中で、当初の出店原則「店舗面積70坪以上・年商2~3億円」を守って出店を進めていては勝ち残れない。前述した「多様な店舗フォーマット」の開発は新しいエリア戦略の布石であった。エリア戦略の歴史をみてみる。
(1)これまで -マーケットサイズ限定のエリア戦略
これまでのエリア戦略は、マーケットサイズの大きいエリアに対し、70坪以上の大型店舗を1店出店し、年商2~3億円を稼ぐというやり方であった。
従って、創業初期の頃は、「繁華街」限定で、東京でも主要3ターミナルである新宿、池袋、渋谷にプラスして上野、御徒町程度であった。現在、山手線内の駅周辺でマクドナルドの空白地帯となっているのは、西日暮里、駒込の2駅しかない。
次のターゲットが、「住宅街駅前」。第1号店は代々木店である。そして、1977年に生活圏・ロードサイドにドライブスルーが登場し、「郊外」へと拡大していった。この郊外における顧客ターゲットを「東京第二世代」と呼んだ。東京出身で、独立後に神奈川や埼玉、千葉の首都圏近県の郊外で生活するファミリー層のことである。1970年代の年間店舗増加数は、平均して20店舗強であった。
1980年代に入ると、首都圏にプラスして、地方の都市部で集客力の高いエリアへの出店が進む。「商圏10万人に1店」を出店目標として、年間店舗増加数は年50店舗、約1県1店のペースで出店していった。
(2)これから -中核店+サテライト店でエリアシェア5%獲得
こうした店舗数拡大路線の中で、1993年には1,000店を突破し、当初の出店目標はほぼクリアした。次の出店目標は「2010年・10,000店」に設定された。現在日本で最も多くの店舗数を誇るチェーンは「セブン-イレブン・ジャパン」で、1998年度決算で、7,800店弱。マクドナルドは1998年12月31日時点で3,000店強だから、約10年で3.5倍にし、CVS並の多店舗展開を図っているのである。
こうした計画の裏には「サテライト店」の確立がある。サテライト店とは月商400万円、年商約5,000万円でも収益を確保できる15~20坪程度の店舗である。
これまで、例えばマーケットサイズ100億円のエリアを設定したら最も集客が見込めるポイントに「70坪・3億円」の店舗を1店出店すればそれでそのエリアへの出店は終わりであった。しかし実際、エリアの中には様々な条件によりマクドナルドのショップにはアクセスできない生活者も存在している。そうした生活者の動向を踏まえ、同エリア内で既存店とのリンクが可能なポイントに小型のサテライト店を配置するのである。
図表2.年間店舗増加数と1店舗当たり売上の推移

そうなると、当然店舗間でのカニバリゼーション(社内競合=これまで既存店で購入していた顧客の流出)が発生し、既存店の売上は減少する。しかし、そうであっても既存店とサテライト店トータルで、エリア内での売上が既存店の売上3億円を超えればいいという考え方である(図表3参照)。サテライト店の出店により、1店当たりの売上は1991年度の2.4億円をピークとして減少傾向にある。1998年度は1.33億円と1億円以上減少している(図表2参照)。
こうした、既存店を「中核店」と位置づけた「中核店+サテライト店」のユニットにより「外食マーケットのシェア5%獲得」というエリア戦略が現在推進されている。
外食業界の戦略を読む
業界の業績と戦略を比較分析する
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。
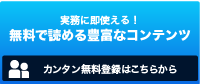
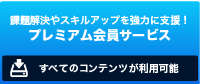
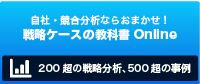
^


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




