次世代自動車は、50万円のソーラーカーへと一挙に収斂し、ものづくりとしての自動車産業はおそらく日本市場では半減し、様々な自動車ニーズを補完する情報、コンテンツやサービス産業が成長するのではないか。既存の自動車メーカーにとってもっとも厳しいシナリオを描くことによって、日本の自動車メーカーの21世紀の戦略を考えてみたい。
(1)2010年はEV大ブレークの年
ガソリンエンジン車に代わる次世代の自動車開発競争が活発化している。今年は日産リーフの登場に象徴されるように、電気自動車が大ブレークの年になりそうだ。経済産業省によれば、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、電気自動車(EV)など次世代車の割合は、2020年に新車販売台数の50%、2030年に70%に達すると言われている。次世代自動車のうちEVが占める割合は25%程度になると予測される。(2)ハイブリッドは過去のβ方式か-EVに一気にジャンプする自動車市場
しかし、この見方は甘い。技術変化はもっとドラスティックで早いものだ。過去、固定電話から携帯電話、レコードからCD、フィルムカメラからデジタルカメラへの置き換えは、新技術の量産開始からほぼ7年しかかからなかった。蒸気機関車と電気鉄道が併存しないように、EVが普及し始めれば7年後には全てがEVに置き換わる。APS(アドバンストフォトシステム)やDAT(デジタルオーディオテープ)のように、どんなにその技術が有用であったとしても、既存技術の延命商品が長く続いた例がない。次世代自動車への置き換えは、こうした前例と同様、ガソリン車からEVへと一気にジャンプする可能性が高い。続々と参入する新興EVメーカーがこの動きを加速している。後発メーカーにとっては、トヨタとホンダが独占し参入障壁が高いハイブリッド市場より、EVに参入したほうが魅力的だからだ。HVはかつてビデオの記録方式の規格争いで破れたβ(ベータ)方式(ソニーが主導して開発したビデオの記録方式。最終的にはビクターが主導し後に現パナソニックを中心にシャープ、三菱電機、日立などが採用したVHS方式に破れた)のように孤立した規格になりかねない危険性を持っているのである。トヨタやホンダが長年の技術蓄積と膨大なコストをかけて開発したHVはもはや、電気自動車に収斂する過程の、過渡的な商品にしかならないのである。(3)コンバージェンスの最終段階は50万円のソーラーカー
次世代自動車の競争は最終的にどのように収斂するのか。結論はEVの先にある「50万円のソーラーカー」(図表1)である。ソーラーカーとは、太陽電池で発電した電気を使って走る電気自動車の一種である。ソーラーカーに収斂する理由は三つある。| 図表1.次世代自動車のコンバージェンス(収斂) |
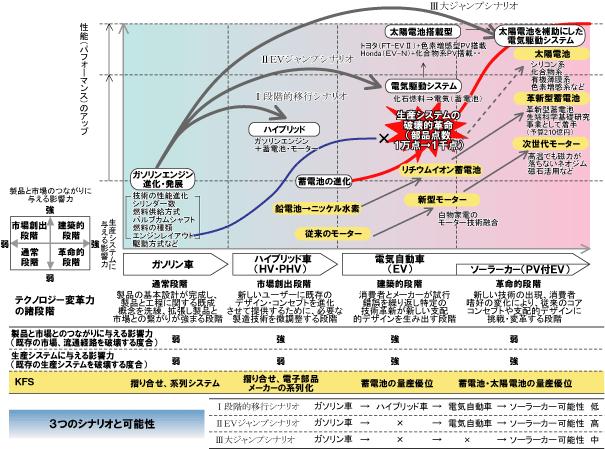 |
まず第一に、電気自動車が実用化段階に入ったことだ。2010年に入り三菱自動車の「アイ・ミーブ」、日産自動車の「リーフ」が個人向けに発売される。中国の電池メーカーBYD、韓国のCT&Tなどの新興企業も続々と電気自動車を今年度中に発売する。2012年前後とされる電気自動車の量産段階に入れば、ガソリン車・ハイブリッド車から電気自動車への置き換えが一気に進む可能性がある。背景にあるのはリチウムイオン電池のエネルギー密度の驚異的な成長である(15年間で5.2倍)。電気自動車の航続距離は現段階で160kmであり、ハイブリッド車の500kmと比べると劣るものの、実はこの航続距離で90%以上の車の利用シーンがカバーできる。次世代自動車の鍵を握る電池技術に対しては、日本の「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」(7年間で210億円投資)をはじめとして、米国、欧州、中国、韓国が国家予算を投じて開発に取り組んでおり、さらなる性能向上が期待できる。さらに、コストが下がる。電気自動車の価格は補助金がなければ400~500万円と高価だが、リチウムイオン電池の価格は量産時には1kWh当たり1,000ドルにまで下がり、ガソリン車の相場とほぼ同等になると言われる。電気自動車へのシフトが前倒しで起きる可能性も出てきたのである。
第二に、膨大な太陽エネルギーを電気に換える太陽電池の技術進化により、電気自動車普及の阻害要因が小さくなることである。電気自動車はバッテリーの容量が大きいことや、充電時間がかかるデメリットがあり、1基200万円もする急速充電機の設置に膨大な社会的コストがかかる。このデメリットが太陽電池によって将来的に解決される可能性がある。地球に届く太陽エネルギーは1時間の日射量で、全人類が消費する1年間のエネルギーを賄うことができるほど膨大なものである。太陽電池は太陽光さえ届けばどこでも電気を作り出せるため、走りながら充電することができる。太陽電池と蓄電池を組み合わせることにより、「リアルタイムの充電」が可能になり膨大な社会的コストを削減することができる。太陽電池を自動車に搭載する場合、設置面積が2㎡、最大出力が300Wとして、利用可能な最大電力量は現状1日当たり0.8~0.9kWhであり、太陽電池の発電電力による走行距離は1日あたり6~7km程度である。しかしシリコンを使わない化合物系太陽電池を使った太陽電池の変換効率が4割台にまで向上しており、現状の1割台から4倍に増える可能性がある。さらに、電気を効率的に使うためのモーターにおいては、ネオジム磁石のように高温でも磁力が低下せずモーターの性能を維持することができる素材の開発や、洗濯乾燥機で蓄積されたモーターの技術を電気自動車で活用する動きも出始めており、太陽電池の電気を使った航続距離は今以上に伸びることが予想される。
第三に、消費市場の世代交代が進むことである。クルマに従来の「走り」や「格好よさ」のような付加価値を求めず、車に関心を持たない若い世代が2020年に消費市場の5割に達することである。この傾向は日本だけでなく、ドイツ、アメリカなど先進国でも進む現象だ。若い世代は、上の世代のようにクルマに200万円も300万円も払う世代ではない。200~300万円のクルマは見向きもされず、50万円で買えるクルマには飛びつく。電気自動車の開発コストは現在、鉛電池や汎用品のモーターにより1台100万円で改造EVがつくれる水準にまで到達している。電池の発電量当たりのコストが5年で1/3~1/2に減少するスピードを考えると、50万円という価格帯もみえてくる。自動車の革命的な変化は電池の進化により間近に迫っている。従来描いていたような、ガソリン車からハイブリッド、そして電気自動車へと段階的に進むシナリオではなく、電気自動車、あるいは太陽電池との一体化により一気にソーラーカーへとジャンプする可能性も出始めている。
| 本コンテンツの全文は、会員サービスでのご提供となっております。 以降の閲覧には会員サービスご登録が必要です。
|
このコンテンツに関する必読コンテンツ


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




