今回はエリアマーケティングの視点を取り入れながら、新しい需要創造型営業のすすめ方を提案したい。
エリアマーケティングの基本は、シェア競争をするのか、新習慣を提案するのかに大別される。当該エリアにおける自社の実績が、シェア水準の格差にもとづくものなのか、普及水準にもとづくものなのかで対策が大きく異なってくるからである。シェア水準が要因であれば、これはもう競争で勝つしかない。競争相手を特定化し、泥臭いこともやりながらシェアを奪うしかない。今回、着目したいのはもうひとつの要因、普及水準の考え方を取り入れた提案営業である。
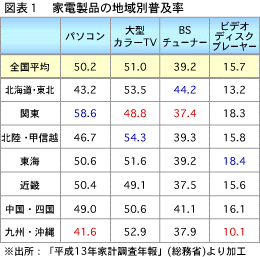
普及水準が問題である場合は、競争よりもお客さまへの啓蒙や提案が重要となる。家電エレクトロニクス製品を例にとってみよう(図表1)。パソコンや大型テレビ、BSチューナーは普及率は60%に満たない。とくに、普及率の低い地域では徹底した啓蒙が必要になる。また、ビデオディスクプレーヤーやデータはないが5.1チャンネルのシアターシステムなど普及率が低い商品では、安さを売りにするよりも徹底した啓蒙が必要である。もっとも効果的な啓蒙方法は、体験である。POPなどで訴求するよりもずっと効果的である。「百聞は一見に如かず」のとおり、体で覚えていただくことが大事だ。事実、低普及率の商品をよく売っている店はこの手法を必ずといっていいほど実施している。
逆に、ある程度の普及率に達した場合、シェア競争をすればよいかというとそれだけではない。ターゲットの切り口を変えることで新たな可能性が見いだせる。パソコンの場合であれば、前年割れが続いているなかで、「中学校入学前の子供がいる世帯」に重点化し成功しているところもある。
普及率という考え方は耐久消費財だけでなく、食品などの非耐久財でも視点を変えれば活用可能である。提案したいのは「指数」という考え方を用いた提案をすることである。
食品の事例で地域別に指数化を試みた(図表2)。この数字は、家計調査をもとに内食費に占める支出費目別の割合を指数として整理したものである。食品メーカーやスーパーの方には、この指数を使って、つぎのような提案を試みてはどうだろうか?お客さまは夕食のメニューに悩んでいると同時に健康にも気を使っている。この場合、ヘルシー指数、ビタミン指数、カルシウム指数を使いながら、自社商品と必要な関連商品(野菜や果物など)を組み合わせたメニューと、健康的な食生活を啓蒙するような情報(POP)をつけて売り場で展開する。提供する情報には指数を必ず入れる。数字があることで、お客さまは客観的に納得できるわけである。とくに全国平均と比較して指数の低い地域で展開すると効果的であると思われる。指数の高い地域は「もっと健康的に」という訴求が必要となろう。
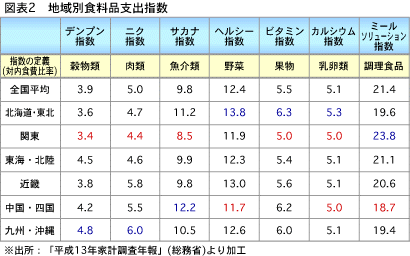
あるいはミールソリューション指数(もしくは逆数をとり「手作り指数」)を使って、手作り風の食卓を働く主婦に向けて提案したり、逆に手作りの重要性を訴求したりすることができるのではないだろうか?
お客さまは、抽象的な文字情報よりも数字情報の方が客観的で納得するし、わかりやすい、ということが言いたかったことである。そうすることによって需要創造型の提案営業が可能となる。一度、試してみてほしい。
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




