経済情勢が不安定な状況にあり、倒産企業や支払遅延企業が多くなっている。平成13年の倒産件数は1万9000件を越え、1984年に次ぐ戦後2番目を記録している。この時期重要なのは、営業の質であり、闇雲に量を追求しては危険だと言うことができる。代金回収もままならない取引先を増やしてもこちらの体質が悪化するばかりだ。
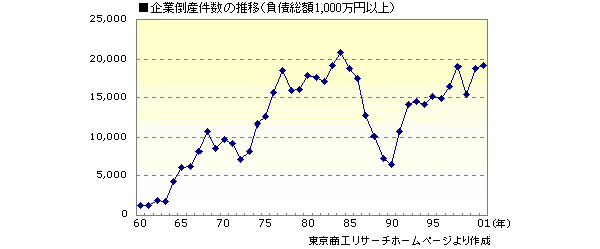
今回提案したいのは、こうした状況を踏まえ、既存得意先への開拓営業を再検討することである。この時期、全くの新規開拓営業にはリスクが伴う。攻めるべきは、取引実績があり、相手の経営情報がある程度掴める既存得意先だ。既存得意先を信用性の指標でチェックし、選別した上で、自社商品を扱って欲しい売りたい得意先にフォーカスして攻める営業である。
具体的に既存得意先を攻めるには、以下に示した三つの評価基準で取引先をグルーピングし、インストアシェアの状況を勘案して、開拓営業のテーマ設定を行う必要がある。
- 既存得意先の業界における経営規模(売上高)
- 信用性ランク(過去の支払い実績や全社的な取引基準など)
- 既存得意先でのインストアシェア(自社取引実績÷(1)で代替可能)
ここで、信用性ランクがDランクなど、基準に満たない得意先を除外して、開拓先リストとする。その上で、得意先の経営規模とインストアシェアでポジショニングする。各グループに具体的にどの得意先が属すのかを見ながらグループ毎に開拓営業テーマを検討する。一般論でいえば、経営規模が大きくインストアシェアが低いグループの中で、開拓可能性の高い取引先の攻略が重点テーマとして浮上してくることになる。
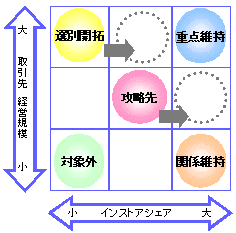
さて、インストアシェアは視点を変えれば、その得意先における自社の拡販余地の指標である。極めて単純に見ればインストアシェアが小さいほど自社の拡販余地は大きいことになる。そして当然ながら、その拡販余地は競合企業が占めている。拡販余地の多寡でなく、拡販余地の質が問題である。最後に三つのパターンを取り上げ、基本的な攻略方向を整理してみる。
(1)インストアシェア50%超の競合企業が存在する場合
得意先のメイン取引企業で、得意先も頼る存在になっており通常攻勢は難しい。この関係が揺らぐポイントを注視することが基本だ。得意先と競合企業の相互の担当者の異動など攻める機会を探索することだ。
(2)得意先のインストアシェアを自社を含め数社が同程度で占めている場合
インストアシェアが10%を越え始めると、得意先への存在感や影響力が出てくる。群雄割拠で競争は厳しいが頭一つ抜け出すためには、競合各社との差別化ポイントを明確にする必要がある。商品、商品組み合わせ、企画提案、商談スタイル、配送サービス、配送スピード、受発注スタイルなど、競合各社にはない役立ち方を探索することだ。
(3)自社が下位グループに属している場合
インストアシェアが10%以下の場合、競合各社への影響力もなく、逆に攻撃を受けたり、得意先から切れられる対象にさえなりかねない状態といえる。早期に一点集中突破できるセールスポイントを準備することだ。今や業界トップにまで登り詰めたアサヒビールだが、1987年のスーパードライ発売以前は「シェアが10%を切る」「酒販店から切られかねない」という危機意識があり、逆にこのことが組織的な営業パワーを生み出した。
参照コンテンツ
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




