- マーケティングの教科書に、マーケティングの「4P」の説明がありますが、その中に「営業」がありません。営業はマーケティングではないのでしょうか?
-
ターゲット市場に対して企業が目的を達成するために、マーケティング機能を組み合わせて統合するものとしてマーケティングミックスという捉え方があります。「4P」とは、E.マッカーシーがさまざまなマーケティングの機能及びツールを四つに分類して「マーケティングの4P」と名づけたものです。それが翻訳され、そのわかりやすさのため広く普及したものと考えられます。この「4P」に「営業」は、登場しません。そのため単純にみると、「営業」が4Pにないように思われますが、マーケティングを体系化したP.コトラーの「マーケティングマネジメント ミレニアム版」の中でも「営業」はプロモーションの中の「人的販売」という1要素として明確に位置付けられています。
一方、日本ではマーケティングは昭和30年代前半にアメリカから導入され、アメリカの教科書を翻訳してマーケティングを学んできました。大筋はアメリカのマーケティングの概念を受容しながら、アメリカとの歴史的な背景や流通構造の違いなど、日本の独自な部分を付け加えて発展してきました。「営業」の位置付けは、日本では人的販売を超えた重要なマーケティングの機能として扱われています(図表1)。いずれにしても「営業」はマーケティングの機能としてあり、日本ではアメリカに比べてより重要なものとして上位階層に位置付けられているということです。
図表1 アメリカと日本における営業の位置づけ
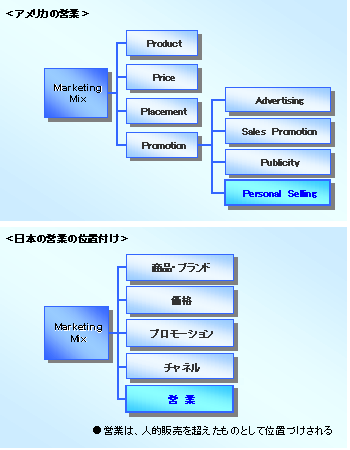
その背景は次のようなものです。
マーケティングは1910年代のアメリカで生まれ、市場と企業の発展とともに概念を発展させてきました。アメリカにおいて成立し発展してきた環境条件と日本とでは歴史的に大きな違いがあります。特に、流通構造には大きな違いがあり、日本の特徴を整理すると、次のようなものです。
- 小売店舗数、密度が日本の方が圧倒的に多い(組織小売業比重が小さい)
- アメリカでは排除された「卸」が一定の力をもって存在している
- メーカーによる流通系列化がすすんでいる
- 長期継続取引の文化がある
この結果、日本では得意先との関係づくりが非常に重要な意味をもち、マーケティング概念が導入される以前から営業が企業活動の中心的な機能として捉えられてきました。
現代においては、メーカーと流通企業との力関係は逆転し、CVS、GMS、ドラッグストアなどの組織小売業企業が優位性を増し、メーカーの営業活動の役割と活動内容が大きく変化しています。
当社では、メーカーの営業活動は企業のコミュニケーション活動を完結させるものとして、「情報提供を通じて取引先と共に顧客満足を創るコミュニケーション活動」と捉えなおしています。
さらに、競争の観点からみると「営業マンの数」「拠点の数」などの量的優位性の競争から営業組織の課題解決力による質的な競争になっていると考えられます。
参照コンテンツ
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

成長市場を探せ コロナ禍から回復し、過去最高を記録したキャンディー
コロナ禍で落ち込んだキャンディー市場は、22年には反転、24年は過去最高を記録した。成長をけん引しているのはグミキャンディーとみられている。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




