今年の白書タイトルは、「拡がる低燃費スタイル、増殖するタッチポイント」としました。後ほど詳しくご報告しますが、「タッチポイント」とは、お客さまとの接点のことを言っています。商品・コミュニケーション・店頭売り場など、お客さまとの接点が、ロングテール化する流通とネットコミュニケーションで膨大にふくれあがっている、という意味において、「接点」とは言わず「タッチポイント」としております。
本日は、白書の概要についてご報告させていただきますが、2013年の消費に関する次の五つの疑問をもとに話を進めていきたいと思います。
- 2013年の消費トレンドは?
- 「食」はどう変わるか?
- 消費者とのタッチポイント(接点)はどう変わるか?
- 顧客説得の鍵は?
- 2013年消費市場の機会と脅威は?
 1.2013年の消費トレンドは?
1.2013年の消費トレンドは?- 主流の価値観は「近縁充実」志向
- 消費の「低燃費」スタイル
- 関係重視消費の浸透
2005年と2012年を比較して最も大きく変化しているのは、自己実現志向です。これは、自分の可能性や夢、理想を追求してランクアップして行きたい、という価値観で、2005年から2006年にかけて下がり、さらに、2011年から今年にかけてさらに大きく下がっています。2005年から2006年にかけては、ホリエモン逮捕や村上ファンドの事件があり、ベンチャー企業長者の挫折、階層格差の拡大が喧伝された時です。そして、出る杭は打たれるという価値観や、格差社会へのあきらめなどによって低下したのだと考えられます。なお、震災後7月の調査では前年と変化はなかったのですが、その後1年間で、「20年後の暮らし向きがよくなっているとは思えない」という長期的な将来見通しが悪化しています。これが自己実現志向低下の要因になっているようです。
他にも「伝統保守」の価値観が昨年から低下傾向にありますが、これは、安心のよりどころになるような伝統的な秩序観がくずれてきているのかもしれません。一方、2005年から上昇傾向にあるのが、「自由享楽志向」と「他者依存志向」ですが、ふたつとも昨年からの変化は小さく、中長期の趨勢といえそうです。
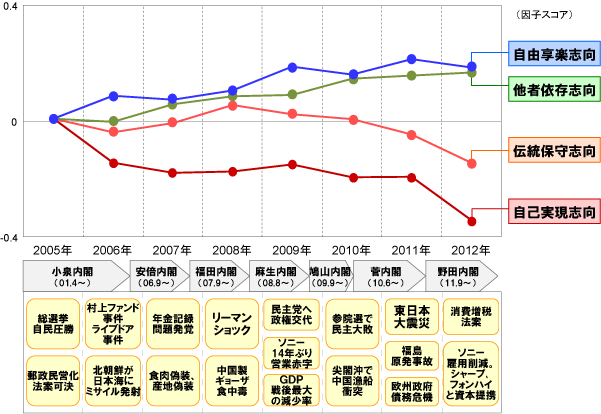
図表2.世帯割合の比較(2005年~2010年) |
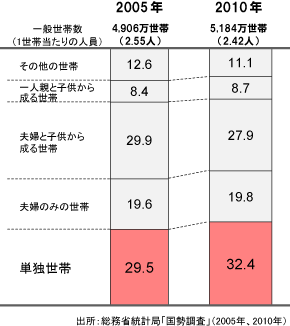 |
図表3.価値意識因子の構成比 |
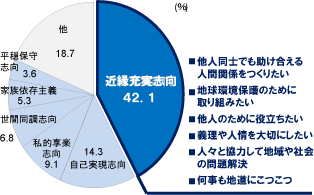 |
図表4.近縁充実志向の世代差 |
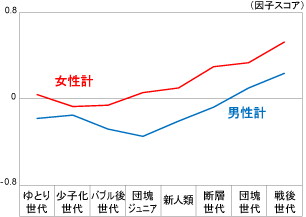 |
一人暮らし層の価値観の特徴は、享楽志向が強いことです。やむをえず1人で住んでいる人もいると思いますが、どちらかといえば、一人でも生活に困らないし気楽でよい、という人が多いようです。また、友達とはネットでいつでも繋がれるので寂しくない、という面があるとも考えられます。
価値観を測定する上で、継続して調査している項目は36項目です。ただ、それだけではなくて、時々に新しい項目を加えての分析も行っています。
今年は、60の変数を使って価値観の潜在因子を分析しました(図表3)。この円グラフは、価値意識因子の構成比を示しており、最も説明力の高い価値観は「近縁充実」志向でした。次が「自己実現」、続いて「私的享楽」「世間同調」「家族依存」「平穏保守」といった六つの志向性があがってきています。
昨年の価値観は「家族の絆」という印象が強くありましたが、それは震災の影響を強く受けたものだったと考えられます。今の日本人の価値観として最もウェイトが高い「近縁充実」志向とは、「他人同士でも助け合える人間関係をつくりたい」「他人のために役立ちたい」など、助け合える人が欲しい、という志向です。では、なぜ「今、近縁充実なのか」を考えると、国や政府、社会が頼りにならず、大企業といえども安定していない状況が関係しているのではないでしょうか。地縁・血縁・社縁が薄れ、安心が喪失している今、その裏返しとして、信頼できる近しい人との関係づくりを再構築して行きたい、という気持ちがあるのでしょう。
遠くの親戚よりも近くの友人、というような「近縁充実」志向が強いのはどの属性なのかを見てみると、性別では、男性より女性、世代別では断層世代、団塊世代、戦後世代という50歳以上となっています。しかし、このグラフ(図表4)をみると、必ずしも若い世代が低い、というわけではないようなので、この価値観がこれからの主流になっていくのでは、と推測できます。
消費意識について
図表5.賛成率50%以上の消費意識 |
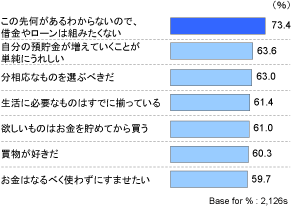 |
図表6.消費意識因子 構成比 |
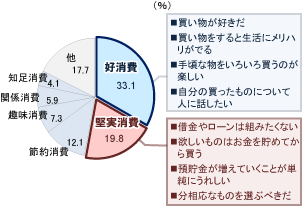 |
図表7.五つの消費意識タイプ |
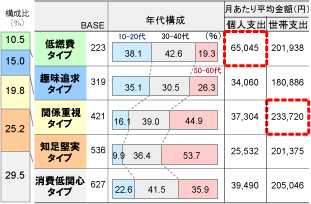 |
図表8.低燃費タイプと関係重視タイプの消費スタイル |
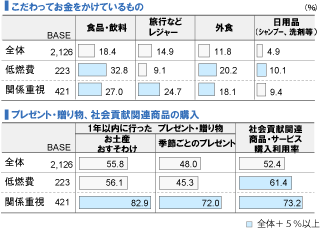 |
ただ、堅実な意識が並ぶ中、6番目に「買い物が好きだ」が出てきています。大きい方向性として、消費に堅実であることに違いはないですが、必ずしも「お金は使いたくない・貯めたい」というだけではない方向性がみてとれます。
次に、消費意識の背景にあるものを分析したいと思います。お金の使い方や買い物の仕方についての全46項目を因子分析にかけた結果、因子構成比は図表7の通りでした。消費意識の背景にある気持ちとして大きい影響力を持っているのは、「好消費」、「堅実消費」と呼べるものであることがわかります。
好消費については、「買い物が好きだ」「買い物をすると生活にメリハリがでる」などの項目から説明できます。ただこれは、どんどんお金を使うということではなく、純粋に買い物が好きで買い物をしたことを人に話したり、手頃な価格のものを買ったりすることで、生活が楽しくなるなあという気持ちになることだと考えています。また、堅実消費については、「借金やローンは組みたくない」「欲しいものはお金を貯めてから買う」など、お金をあまり使わず堅実に貯めていくような気持ちです。
この「好消費」と「堅実消費」のふたつの気持ちは、一見相反しているようで実は同居しているものだとも考えています。これが、現在の消費に対する全体的な意識です。
全体の消費意識を踏まえたうえで、人をタイプ別に分類した結果が図表7です。低燃費タイプ、趣味追求タイプ、関係重視タイプ、知足堅実タイプ、消費低関心タイプという、全部で五つのタイプに分けて理解することができます。図表7で見ると、低燃費・趣味追求タイプは、10~20代に多く、関係重視・知足堅実タイプは50~60代に多いことがわかります。
五つの中でも、特に着目できるのは低燃費タイプと関係重視タイプです。その理由はふたつありますが、第一に、このタイプの消費意識や価値意識が、世の中の主流に近いことが挙げられます。低燃費タイプと関係重視タイプの価値意識は、伸長している「近縁重視」の傾向が強く、低燃費タイプの消費意識は、好消費と節約消費の両面を強く持っています。第二に、月あたりの平均支出金額を見ると、両タイプともに支出金額が多いことが言えます。低燃費タイプは個人支出が6万5,045円、関係重視タイプは、世帯支出が23万3,720円となっています。
低燃費タイプと関係重視タイプの消費の特徴について、もう少し具体的にみていきましょう。
それぞれの消費タイプの人がこだわってお金をかけているものについて、耐久財等を含む全24カテゴリのうち特に特徴のあるものを抜き出したところ、両方のタイプで「食品・飲料」、「外食」と、食べる物が全体と比べて高い結果となりました。タイプごとに特徴的だったものとしては、低燃費タイプは最寄り品と呼べるような、ひとつひとつの金額は小さいもの、関係重視タイプでは「旅行などレジャー」にお金をかけていることです。また、いずれも車・家電・インテリアなど、耐久財や比較的高額のものは入っていないようでした。また、プレゼント・贈り物、社会貢献関連といった、自分以外に向けた消費でみると、関係重視タイプは全体に比べて高いことがわかります。
まとめると、低燃費タイプは最寄り品に近いもの、関係重視タイプはギフトや社会貢献などにお金を使い、特に関係重視タイプは自分ではなく人を喜ばせることにこだわって支出を行っているようだ、と言えると思います。
より具体的に、低燃費タイプの消費、「低燃費スタイル」がどのようなものか見ていきますが、低燃費スタイルは、「仲間と一緒に楽しめる」「その場で参加・体験できる」「手軽に食でトレンドを楽しめる」という三つのキーワードから理解できます。
仲間については、使っている方も多いかもしれませんが「LINE」が代表的なものです。「LINE」は、身近な仲間と、絵文字のようなスタンプを使って連絡しあったりコミュニケーションしたりできるサービスです。基本的には無料で利用できますが、スタンプの種類を増やすためにスタンプを購入することもあります。1シリーズ40種類で170円。ひとつあたりの金額は小さいが、これを気兼ねなくどんどん買っているようです。
参加体験では、お台場のダイバーシティ東京に見られるように、ZARAやforever21、H&M、ABCマート、ユニクロなど、ファストファッションの宝庫のようなモールが代表的です。実際に足を運び、2,000~3,000円の手頃な服を何着も買って楽しむイメージです。H&Mがかっこいいとかかっこ悪いとか、ブランドへのこだわりはなく、「そこそこのもの」を買って楽しんでいるのでしょう。
食トレンドの例では、スライム肉まんが挙げられます。販売していたのは1年ほど前ですが、1個170円で売り出しており、手頃な価格でトレンド感を楽しんでいたようです。写真はtwitterのものですが、ただ一人で買って食べるだけではなく、人に伝えて楽しむような広がり方もあるようです。
低燃費タイプの人は、「ケチケチしている」、「お金を使うのが嫌い」ということではなく、それなりに好きなものに消費をしています。また、ひとつひとつの金額は小さいですが、ちまちまとバラエティ豊かに買っている間に、支出金額が高くなっているような人達です。

図表10.超高額支出者が こだわってお金をかけているもの |
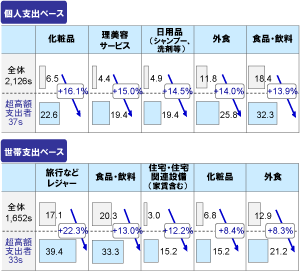 |
これらの超高額支出者では、個人では化粧品や理美容・健康サービス、世帯では旅行やレジャー、食品・飲料など、耐久財等ではなく、最寄り品やサービスなど形がないようなものについてこだわっていることが明らかになりました。これは、ここまで着目してきた低燃費タイプや関係重視タイプと同じような傾向となっています。
 2.「食」はどう変わるか?
2.「食」はどう変わるか?図表11.ある日の夕食実態 |
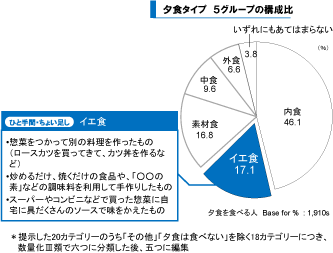 |
図表12.「イエ食」とは |
 |
まず、ある平日の夕食に、人々はどのようなものを食べているのかを調査しました。回答を分類した結果は図表11のとおりです。伝統的な生鮮品から作った「内食」、お惣菜や弁当などを買ってきて食べる「中食」、レストラン・居酒屋などで食べる「外食」、果物や野菜など素材をそのまま食べる「素材食」という分類に加えて、新しい分類の「イエ食」という食事スタイルがあることが明らかになりました。
イエ食とは、お惣菜や加工食品にひと手間加え、味を変えて楽しむ食事スタイルのことを指しています。今回の調査結果を見ると、全体としては、伝統的な食事である内食が依然として半数を占めており、しかし、その内食に次いで多い食スタイルが「イエ食(17.1%)」で、中食(9.6%)の割合を上回っていることがわかります。
では、「ひと手間を加える」イエ食とは具体的にどのようなものか写真を見ながら紹介したいと思います。この写真はイエ食レシピをピックアップしてきたものですが、右下の写真は、冷ややっこにザーサイとおかずラー油をかけ、具だくさんのソースでひと手間を加えたものです。また、左上のカレーは、焼き鳥の缶詰めと野菜ジュース、カレー粉を使ったカレーで、缶詰めやジュースなどの加工食品を活用することで、煮込む手間を省いている食事となっています。右上は、"キャベツのごまみそいための素"という、本来であれば野菜と一緒に炒める調味料をアレンジし、いり豆腐を作っていて、これもイエ食となります。左下は、最近品ぞろえが充実しているコンビニ惣菜を組み合わせたもので、厚焼き卵にさんまの蒲焼をのせ、ネギをちらしたおつまみです。
このようなレシピを見ると、イエ食の特徴は、複数の加工食品を組み合わせていることだと考えられます。ただ単品の惣菜を買ってきてレンジでチンして食べるのではなく、複数を組み合わせて味をアレンジして食事を楽しんでいると言えるのです。
最近では、缶詰めを使ったレシピ本や、セブンプレミアムのお惣菜でできるメニュー本も発売され、身近ですぐ手に入る加工食品を活用するメニュー提案が増えています。さらに、調査からわかったイエ食のもうひとつの特徴として、ビール類や缶チューハイ、カクテルなどのソフトアルコールが、イエ食とともに飲まれていることが多い、ということがありました。
図表13.属性別夕食タイプ分類 |
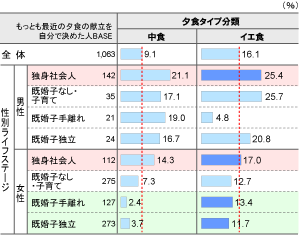 |
図表14.夕食タイプ別 献立を決めたタイミングと 調理時に参考にする情報 |
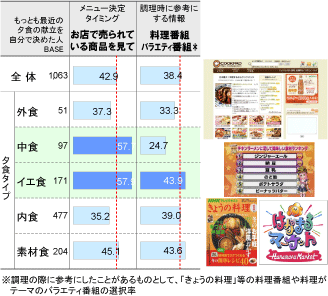 |
続いて、イエ食のメニューはどのように決定されているのかを見てみます。図表14の左側は、メニュー決定タイミングを調査した結果ですが、他の食事と比べると、中食、イエ食ともに店頭決定率が高いことが特徴的です。お惣菜などの加工食品を使うことから、店頭のお惣菜を見てメニューを決定しているのだろうと推察できます。また、イエ食のもうひとつの特徴として、情報食であるということが言えるようです。
右側のグラフは、調理をする時に料理番組や料理がテーマのバラエティ番組を参考する人の比率を示したものですが、イエ食に関しては、内食と同等に料理番組などのメディア情報を参照して調理されていることがわかります。
中食は店頭でメニューを決めて購入し、そのまま食べるものですが、イエ食は中食をそのまま食べるのでは味気がないから、メディア情報を参考にもっと食事を楽しむ、というスタイルの現れではないかと考えられます。
 3.消費者とのタッチポイント(接点)はどう変わるか?
3.消費者とのタッチポイント(接点)はどう変わるか?まず、どの商品購入チャネルが伸びているかを見ていきたいと思いますが、食品スーパーやネット通販での人々の評価を見ると、共通して「品ぞろえの豊富さ」が高く評価されており、ロングテールチャネルの伸長が明らかです。また、先ほど紹介したイエ食に対応した食品購入チャネルが、今後伸びていくだろうと推測できます。
ネットショッピングについても、今や日常生活に浸透して久しいですが、その勢いはますます強まっていることが確認できます。そして、今後、流通のネット化がどんどん進むことが予測できます。
このグラフは、各チャネルの1年以内の利用率を見たものです(図表15)。利用率の1位はコンビニ、続いてドラッグストア、GMSと、リアルチャネルが上位を占めており、利用頻度が増えているチャネルを見ると、コンビニ、食品スーパー、インターネットショッピングサイトとなっています。なお、伸び率でみると、ネットショッピングは二桁となり、他のチャネルを大きく引き離していることがわかります。
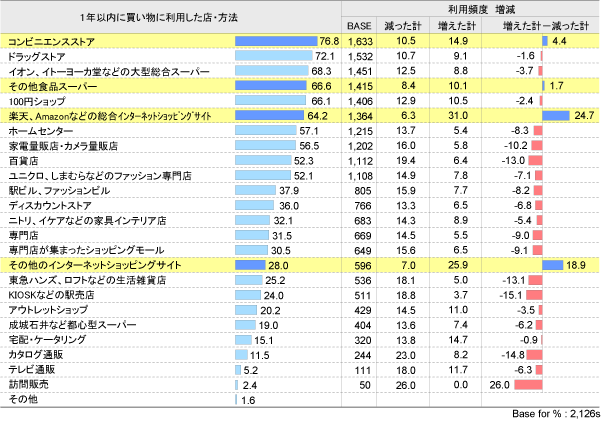
図表16は、コンビニ、食品スーパー、ネットショッピング、それぞれのチャネルを利用したことがある人に、利用理由を尋ねたものです。コンビニや食品スーパーなどは「自宅から行きやすい場所にある」という立地条件が利用理由として多く、アマゾンや楽天などの総合インターネットショッピングサイトは、「品揃えが豊富」「珍しい商品が多い」「ふだん自分では探さない商品を見つけることができる」など、品揃えに関する項目が上位を占めています。つまり、ロングテールが成長のカギとなっていることがうかがえます。また、品ぞろえの豊富さについては食品スーパーでも利用理由として挙がっており、消費者により重要視されていることは品揃えの幅広さであることが見てとれます。
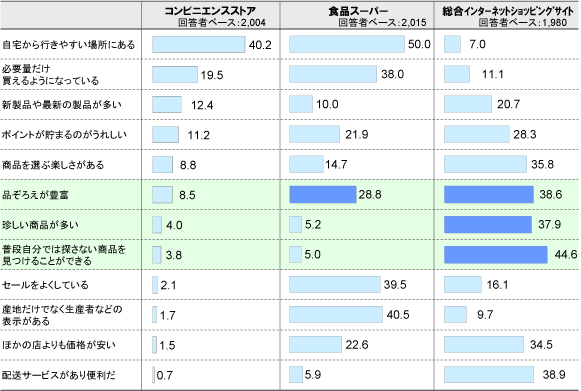
図表17.夕食タイプ別高頻度利用チャネル |
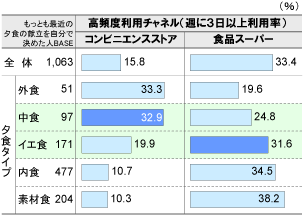 |
図表18.堅調なリージョナルチェーン |
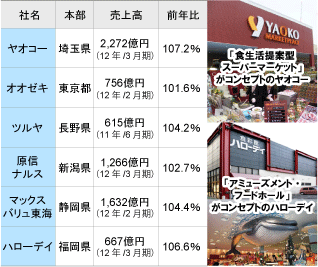 |
図表17は、夕食タイプ別に、コンビニと食品スーパーの高頻度利用者(週に3日以上利用する人)の比率を出したものです。中食では特にコンビニの利用率が高く、全体の2倍以上になっています。イエ食では、コンビニも全体を上回る高さになっていますが、食品スーパーがより多く使われていることがわかります。つまり、食品スーパーの伸びているひとつの背景として、イエ食という新しい食スタイルへの対応が考えられます。
食品スーパーの中でも、特に堅調なのは地域に密着したリージョナルチェーンです。埼玉のヤオコー、東京のオオゼキ、福岡のハローデイなど、業界全体がマイナス成長の中、これらのスーパーはいずれも前年比プラスとなっています(図表18)。簡単に各社の工夫を見てみると、例えばヤオコーは食生活提案型のスーパーで、お店に入ればその日の夕食のメニューが決まるような売り場作りがされています。例えば、生鮮品売り場に「鍋の素」などの調味料を置いたり、レシピを並べたりするなどの工夫をしています。また、ハローデイでは売り場がディズニーランドとも言われるほど商品が充実しています。これらリージョナルチェーンに共通しているのは、価格競争をしていないということと、売り場での情報発信力や品揃えの良さが挙げられます。
食品スーパーが伸びているふたつ目の理由として、食品スーパーは衝動買いチャネルであるということが考えられます。図表19は、食品、飲料、化粧品などの最寄り品を、買う予定がないのに思わず買ってしまった衝動買いについて、経験がある人の利用チャネルと理由を示したものです。食品の衝動買いは最寄り品の約8割と非常に高い比率で発生しており、その中でも3割が食品スーパーで起きています。
では、衝動買いがなぜ食品スーパーで起きるのでしょうか。当然、「安いから」という価格の要因はあると思いますが、「大量に陳列されていた」「流行っている商品だった」など、価格以外の要因で買ってしまったという人も約4割を占めています。つまり、商品は安くすれば買ってもらえるのではなく、品揃えや売り場づくりといったものが関わっていて、それこそがリアルチャネルにおける今後の伸びを左右すると考えられます。
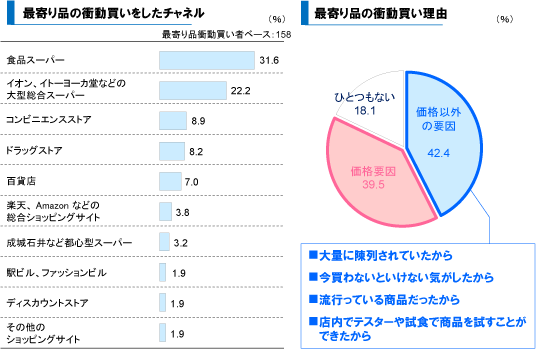
図表20.インターネット購入品目の実態 |
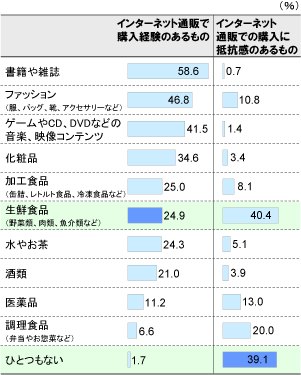 |
ここで注目できるのは、購入に抵抗感のあるモノが「ひとつもない」と答えた人が約4割いるということです。この調査はネット調査だったので、回答者が比較的ネットを利用することに抵抗感が少ないとしても、4割は何でもネットで買えると答えているのを見ると、今後のネットチャネルのさらなる伸びを見込むことができます。
 4.顧客説得の鍵は?
4.顧客説得の鍵は?これに対する答えはふたつです。ひとつは、人々の情報ネットワークを分析していくと、「ブリッジ」と「スピーカー」という役割を果たしている人が鍵となる、ということです。また、もうひとつは、情報メディアのメドレー化によって、情報量と波及スピードが拡大していることです。この結果、一人の人を説得する接点は、膨大になっていると言えます。
図表21.ネットワークタイプのモデル図 |
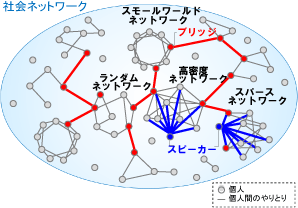 |
図表21は人々の情報交換ネットワークをモデル的に示したものです。●が人で、情報交換の相手同士が線で結ばれている状況を示しています。情報交換をしている人間関係の基本は家族ですが、人によって、仕事関係や趣味、近所づきあい、ネットでの知り合いなど、様々な人とやりとりをしています。
このネットワークのあり方はいくつかのタイプに分けることが出来、例えば、お互いが知り合い同士で密な関係にあるのは「スモールワールドネットワーク」、知り合い同士でかつ人数の多いのが「高密度ネットワーク」、人数は多いがバラバラなのが「スパースネットワーク」という感じです。
また、情報を広げていくのに重要な役割を果たしているのが、複数のネットワーク同士をつなぐ「ブリッジ」の役割をする人です。そして、おしゃべりで、ネットワーク内で多くの人とやりとりする人を「スピーカー」と呼んでいます。このふたつの役割の人に、おもしろくて他人に話したい情報が渡ると、短期間で多くの人に情報が波及していく、という図式になっているようです。
では、ブリッジとスピーカーはどのような属性の人なのかを見たいと思います。まず、スピーカー役ですが、昔から周りにいたのではないでしょうか。他人の情報を妙に知っていて、他の人にペラペラと話す拡声器タイプの人です。女性の50代60代に多くて、全体の約25%を占めています(図表22)。また、ブリッジ型は、男女とも20代30代の層に多いのですが、どちらかといえば男性の方が女性より多いです。男性の20代30代は、ブリッジ型全体の約24%を占めています。
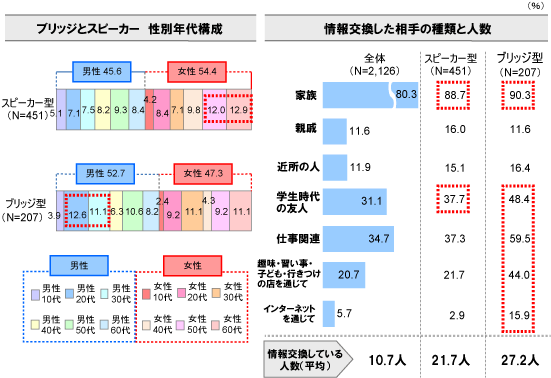
価値観の特徴としては、両者ともに自己実現志向が高い人に多く、自分の体験を他人に伝えたいという志向性があると考えられます。なお、スピーカー型は特に近縁充実志向が強く、他人との関わりを求めて情報交換に積極的な人であることがわかります。
彼らの情報交換の相手をみてみると、スピーカー型は家族に加え、友人や会社関係の人を含めて平均21.7人とやりとりをしており、ブリッジ型はさらに人間関係の幅が広く、人数も27.2人と多いことがわかりました。
実際に、ブリッジとスピーカーはどのように情報を拡大するのでしょうか。事例として、2011年にヒットしたドラマ「家政婦のミタ」の視聴プロセスを分析し、考察してみました。
「家政婦のミタ」は、視聴率調査によると最終回の視聴率が40%と、今世紀に入って最大のヒットドラマでした。我々の調査でも、第一回から最終回、放映が終了した後に見た人も含めて、累積で38.5%の人が見ていたことがわかっています(図表23)。第一話を見た人の中で、スピーカー型の74%の人が、他人に「ミタ」の話題を話しており、ブリッジ型では、話題にした率は平均並なものの、複数のネットワークに発信していると考えられます。第二話以降になると、スピーカー型では、やりとりする人数が多いからか、自分も他人から「ミタ」を見るように勧められることがあり、さらに自分でも他人に話をする、という行動をとっています。また、二話以降に見始めた人は、「視聴率が高いと聞いたから」や、「周りで見ている人が多いから」というような、同調行動をもとに視聴した人がいました。
スピーカー型が多くの人数に伝え、ブリッジ型が家族だけではない自分の知り合いに伝え、互いに「このドラマはおもしろい」ということを話題にした結果、ユーザーがユーザーを説得してどんどん情報が拡大したのでしょう。
ちなみに、「ミタ」とは別に、最近の食品で話題になった塩麹についても同様に分析したところ、購入率は全体で24%に達したものの、スピーカー型とブリッジ型の情報発信が少なくなったことで、ブームはほぼ収束しています。ということで、普及率の差は、ブリッジ型とスピーカー型の働き方の違いにあると言えます。
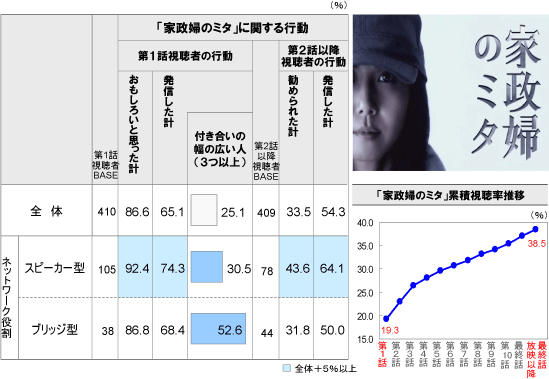
図表24.ネットワーク役割別の行動 |
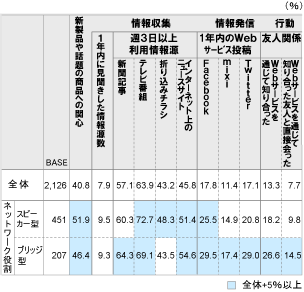 |
ロングテール型の流通と、多メディアと接触して情報のメドレー化を進める顧客が、情報と店頭のタッチポイントを膨大なものにしていると考えられるのです。
図表25.2013年消費市場の機会と脅威 |
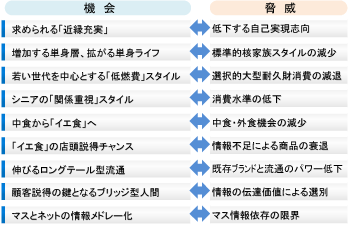 |
機会として九つのポイントを挙げました。全体的にみて、新しいものを先取りするチャレンジャーにはチャンスですが、同時に、保守的スタンスの人には脅威になることが明らかです。
消費トレンドにおいては、価値観の方向性として、「近縁充実」志向に接近するコンセプトがチャンスとなります。一方、自己実現志向の衰退は、ランクアップを想定したものづくりやコンセプトにおいては、ズレが大きくなることがあります。
- デモグラフィックで増加する生活は単身ライフです。したがって、標準的核家族世帯のライフスタイルを前提としたものには脅威となります。
- 消費スタイルとしては、若い世代を中心とした「低燃費」スタイルへの対応がチャンスであり、逆に、選択的大型耐久財にとっては厳しい状況となります。
- シニアの「関係重視」スタイルは今後伸びることが予想されますが、モノを中心とした消費水準は、全体的に低下する可能性があります。
- 食に目を向けると、「イエ食」が伸びそうだと考えられます。現在も、カップ麺よりも袋麺が伸びており、マクドナルドや牛丼大手は弱っています。
- イエ食は情報主導なため、情報次第でヒットにもなるし、廃れもします。情報をどのように発信していくかがポイントとなります。
- 流通では、ロングテール型の流通対応が求められ、既存のマスブランドと既存流通はパワーを低下せざるを得ません。
- 顧客説得の鍵は「ブリッジ型」だが、情報に価値がないと判断されれば、その情報は選別されてしまうことがあります。
- 情報のメドレー化は量的な情報拡大を促進するが、マス情報だけに依存することの限界を示しています。
これで発表は以上です。ご静聴ありがとうございました。
詳細は、消費社会白書2013をご参照いただければ幸いです。
本論文に関連する統計データ


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




