| 戦略的マーケティングのためのミクロ経済学入門 第1章 需給均衡の考え方 :需要と供給が生み出すゴールデン・クロス |
|
| 菅野 守 | |
| |||||||||||||||||||||||
| 第1節 ミクロ経済学の考え方と方法論:概説 | |||||||||||||||||||||||
1.経済学とは(1)本稿で採用する定義「経済学とは、経済社会における経済主体、すなわち個人(消費者または家計)や企業や政府による、財またはサービスの配分・生産・分配に関する合理的行動の分析を行う学問」です。(2)上記定義の吟味1)経済学における分析の対象:実際に観察される経済主体の行動、及び、その集大成としての経済現象 2)経済学における分析の基本前提 :経済主体の"合理的"行動
では"市場機構"とは、一体何なのでしょうか? 以下にて改めて、議論することとしましょう。 2.市場機構とは(1)本稿での定義「市場機構とは、利用可能な技術・資源量の存在・消費者の選好などの情報を(価格などの変数との対応関係として表現される)諸々の財の需要条件及び供給条件という形で集約しつつ、(主として)価格の変動を通じた諸々の財の需給調整に基づいて、財配分の決定・生産技術の選択・分配の決定という三つの問題を解決していく仕組み」です。(2)市場機構の核をなす要素1)財の需要条件 ~ 需要関数「D=D(P;Zd )」として体現されます
2)財の供給条件 ~ 供給関数「S=S(P;ZS )」として体現されます
3)価格の調整を通じた、需給調整
(3)市場機構を通じて実現される、財配分の決定・生産技術の選択・分配の決定のあり方:見取り図
(4)市場機構の機能並びに価格の役割に関する、基本的分析手法大別すると、以下のふたつです。
1)一般均衡分析:前記、生産物市場と生産要素市場の場合のように、関連した市場の間での相互依存関係を明示的に考慮して、複数市場を同時に分析する手法
2)部分均衡分析:あるひとつの財の市場に焦点を絞った上で当該財の価格の変化が他の財の市場に及ぼす影響を捨象し、且つ、他の財の価格を所与として一旦分析を進める手法
(この場合、他の財の価格をパラメターとして取り扱い、その変化の影響を別途考慮していきます) (2003.10)
| |||||||||||||||||||||||
|
|

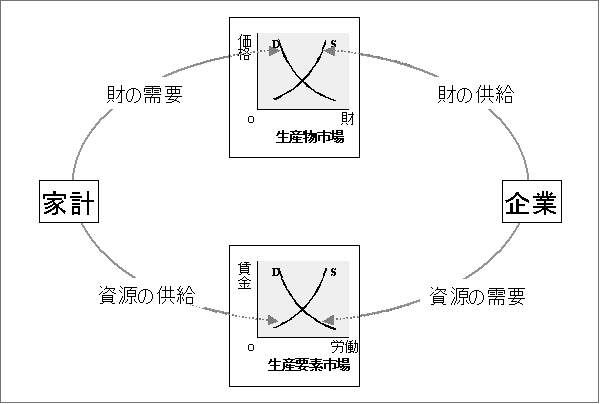

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




