小売業の業績低迷が続いて久しい。日本チェーンストア協会のデータでみると、既存店売上高は42ヶ月連続でマイナスが続いたことはご存じだと思うが、店舗数は平成12年5月以降28ヶ月連続マイナス、そして大型店出店により増え続けていた総売場面積も昨年11月以降マイナスに転じ、現在では前年同月比85%という状況にある(図表1)。
図表1.スーパーの店舗数、売上、売場面積の推移
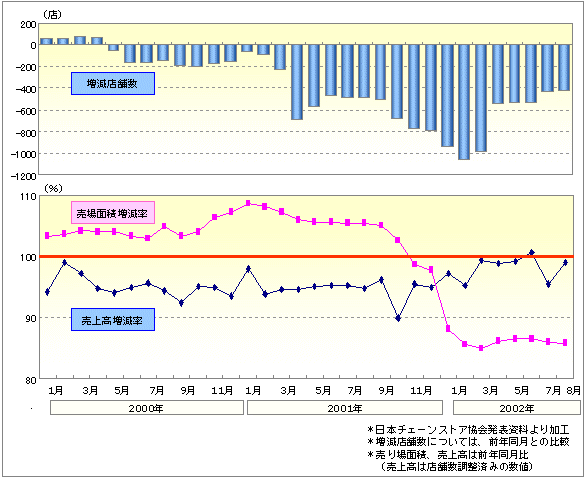
このような状況下で小売業は大きな方向転換を図っている。ダメな店はスクラップし単店を強くしていく試みである。わかりやすくいうと、店舗の権限を強くし、立地する商圏にあわせて店独自の品揃えや売り方を取り入れるようにしたことだ。ということは、我々営業に求められていることは、個店対応を強化することだ。バイヤーに全店統一の提案をもっていっても、条件要求されるのがみえているし、たとえバイヤーレベルで商談が成立したとしても個店での実施率は低くなる(一説には30~40%)。
しかしながら、1店1店対応するのは非常に面倒であるし、現実問題なかなかできない。
どうするか。対策はふたつある。担当企業のなかの拠点店を丁寧にフォローしていく方法とストアタイプ別の企画提案をしていくことだ。今回、提案したいのは後者のアプローチだ。
すでにいくつかの企業でこうした取り組みが始まっている。あるCVSでは、ガムの棚割展開を変えた。オフィス街立地は当然OL客が多いので、タブレット系、つぶガムをゴールデンゾーンに、ロードサイド立地のタイプでは車での利用が多いので眠気ざましや板ガムをゴールデンゾーンにフェーシングしている。また、あるメーカーでは店舗パターンと特徴を整理したリストを持っており、棚割提案やエンド売り場提案の時に「この売り場づくりはこのパターンの店でやりましょう」という提案をすることで成果を上げている。
図表2.業態別ストアタイプ
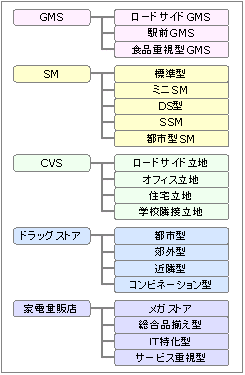
ほとんどの小売業は、いくつかのストアタイプやフォーマットをもっている。ストアタイプを分ける軸は、立地、売場面積、品揃え、ストアコンセプトと企業によって様々だ。担当する企業にあわせたストアタイプ別の店舗リストをつくり、タイプにあわせた提案をしてみてはどうだろうか?これを受け入れないバイヤーは、よほど感度が悪いと考えて良い。その際は、スーパーバイザーやエリアマネジャークラスに提案してみるといい。彼らの方が企業方針を着実に理解し実行できるし、実際、こうしたアプローチをしてバイヤーを納得させているケースもある。
参考までに主要な業態のストアタイプの切り口を整理してみた(図表2)。これをたたき台にして担当企業へのストアタイプ別の提案活動にトライしてみてほしい。
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




