消費低迷が続き、営業現場に手詰まり感が蔓延している。手詰まり打破のひとつのヒントとして今回は、「気温」と「消費」に着目した営業の切り口を提案したい。
日中最高気温がある水準を超えると売れる商品がある。ビール、エアコン、アイスクリームは20℃、水着は24℃、うなぎ蒲焼・日焼け止めクリームは28℃を超えると売れ始める。逆に手袋は13℃、ジャケットは10℃をきると売れ始める。気温と消費のこのような関係は誰もが生活感覚として持っている。この感覚を店頭提案活動にいかすことが大切である。
図表1.気温と売れる商品
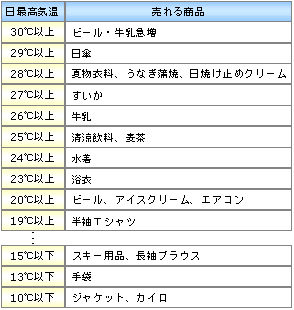
現在、日本の小売業は、CVSを除いてどの業態も売場生産性が落ちている。どの小売業も売場生産性を高めてくれるアイデアを求めているはずだ。当たり前の生活事実に基づいたタイミングのよい確実な店頭提案が、店頭集客力を高め、店頭での具体的な売りをつくり、日々来店してもらう店づくりにつながる。
図表2.業態別売場生産性(坪効率)の低下
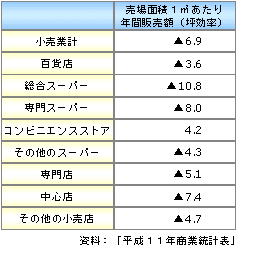
さて、気温と消費との関わりに着目したとき、どんな営業活動が考えられるか。
ひとつは、気温との関係から自身が担当している商品が売れるタイミングをつかんでみることである。タイミングがつかめれば年間のスケジュールがたてられる。いつどんな時期に店頭スペースを確保すればよいか、どんなテーマで何を陳列するか、いくつかアイデアをまとめて、小売説得の材料に使ってみることである。先にあげた食品・飲料・衣料・家電はもとより、もっと他にも気温と売上が関連する商材があるのではないか。
ふたつは、日々気温に気を配り機動的に動くことである。期初にたてた年間販促スケジュールもその時々の気温によって、店頭展開をはやめたり、遅らせたりすることが大切である。それによって店頭フォロー部隊やデモンストレーターの投下など人の動かし方も変わるだろう。
三つは、地域の差に注目することである。同じ担当エリアの中でも山間部と海岸部、東部と西部では微妙に気温が異なるだろう。気温がある水準に達するタイミングも異なるだろう。
このような地域差をも踏まえて各店にタイミングよく店頭展開をすることも大切である。かなり広範囲な地域を担当している営業マンはこのことがより重要になる。
気温がある水準を超える(下回る)決定的なタイミングと場にいかに店頭ツール、店頭フォロー部隊などの資源を集中させるかが営業マンの腕の見せどころのひとつである。
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




