ものごとには法則というものがある。今回は営業対象、つまり得意先へのアプローチについての見直しを提案したい。統計の法則として、よく言われるのが「3:7の法則」というものである。この法則は一般に広く知られているものの活用されていることは意外に少ない。
「3:7の法則」というのは、例えばこういうことだ。3割の得意先で売上の70%を占める、というように重点となる得意先でおおよその売上を占めるということだ。ところが現実は、この法則を無視しているケースが多い。
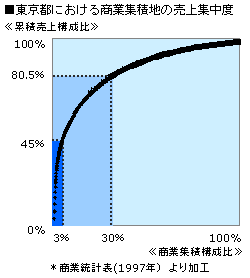
エリア別営業担当制を採っている企業を例に、実際のデータで確認してみる。東京都には約900の商業集積がある。この商業集積地の売上の上位集中化傾向をみてみると、つぎのことが確認できる。実に3%の商業集積地で売上の45%を占め、30%の商業集積地で8割の売上を占める(図表参照)。この場合、3%の商業集積地に重点を定め、徹底した営業活動をすすめることが目標必達の近道となる。現在ではトップシェアを誇る某ビールメーカーが採用してきた営業戦略である。当たり前の地道な活動を徹底してきた成果である。
こうした事実を捉え直した効率的な営業活動をすすめていく必要がある。小売業の出店ラッシュと店舗のスクラップ&ビルドがすすむなかで、集客力のある商圏が変動している。家電でいえば、秋葉原や日本橋の衰退であり、ビックカメラやヨドバシカメラが出店している都心商業集積への顧客集中である。これは典型的な例であるが、こうした現象が至るところで起きているはずだ。今一度、得意先の優先順位を見直す必要がある。我々は得意先を自社売上で判断しがちであるが、得意先の販売力という観点から、いわゆるABC分析をしてみる必要がある。そうしてみると、重点得意先の見方が変わるはずだ。重点得意先への徹底した集中営業が必要なのである。
エリア別営業組織を採っている場合は、都市部への徹底した集中営業にチャンスがある。東京を中心に都心部の商業集積が元気である。こまめに現場を歩いていくと、思わぬ新規開拓先やこれまで軽視していた得意先への提案が必要なことがわかるはずだ。これを組織的に展開している企業が今、シェアアップを実現している。大手企業は過去のしがらみもあり、この重点化ができない。弱者の視点からの営業活動が意外と効果を発揮する。
また有力な組織小売業本部を担当している場合でも、この法則を活用した営業活動が有効である。あるメーカーでは、有力組織小売業に対して、つぎのような提案営業を推進している。このメーカーは有力組織小売業に対して、半期ごとの販促カレンダーを提案し、販促実施状況に対して協力金を支払っているが、展開する店舗は有力店に絞っている。具体的に言うと、販促展開は上位30%の店に重点化し、協力金はその有力店にしか支払わない、もしくは有力店以外で実施しても協力金はわずかしか出さないというものだ。
当たり前のことであるが、営業マンなりに重点得意先は設定している。しかし、それが変動しているという認識はあれど行動に移す例は少ない。やるべきことがたくさんあり、時間が足らないとぼやく営業マンが多いが得意先を見直すことで効率的かつ効果的な営業活動が実践できるはずだ。単純な統計の法則を今一度活用する必要がある。
おすすめ新着記事

成長市場を探せ コロナ禍からの回復続く居酒屋業態 けん引車はネオ居酒屋か
コロナ禍で大きな打撃を受けた居酒屋が回復を続けている。けん引しているのは、「ネオ居酒屋」「ネオ大衆酒場」などといわれる業態や、特定のメニューに特化した業態だ。

消費者調査データ チョコレート 首位「明治チョコレート」、追う「ガーナ」、再購入意向上位にはプレミアムチョコレートも
カカオショックのなか、最需要期を迎えたチョコレート市場。調査結果では明治チョコレートが首位で、「失敗しない」安心感のあるロングセラーがそれに続く。再購入意向首位にはリンツで、プチ贅沢需要もうかがえる。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 主食・米の値上げを8割が実感 価格と品質の間で揺れる食卓
日本人の主食である米は、値上げが続くなか、食頻度の減少が増加を上回る一方、品質を重視する層もみられ、消費者の中で「こだわり」と「節約」が並存していることがわかる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




