超優良企業の代名詞とされるソニーでさえも、1999年3月期連結決算で減収減益を記録した。一方、子会社であるアイワは、11期連続の増収、3期連続の増益を達成し、不振の家電業界の中で唯一高成長を謳歌している。そのアイワは1980年代半ばの円高AV不況により深刻な経営危機を経験している。
アイワはこの経営危機を契機に原理原則を踏まえ、海外生産シフトを柱に円高対応力の強みを基軸とした体質強化を断行した。結果、短期間で業績回復を果たし、現在に至る強みを継続的に構築してきた。
図表1.アイワの業績推移

1985年のプラザ合意を背景として、円が急騰し、日本経済は円高不況に陥る。
- 1985年:240円台
- 1986年:160円台
- 1987年:120円台
この円高不況期、特にAV機器の輸出を事業の中心に据えていたアイワは減収減益、赤字転落し、創業以来の経営危機に瀕する。
- 1986年11月期:売上高410億円、営業赤字43億円
この1986年に副社長としてソニーから移ってきたのが、卯木肇(現・日本デジタル放送サービス(スカイパーフェクTV)会長)である。ソニー時代、単身で米国市場を開拓し、ソニーの名を世界に知らしめ、「販売の神様=ボーン・セールスマン(生まれながらの商売人)」とまで称された氏はアイワでは「経営の神様」と畏怖されるほど、短期間でアイワを生き返らせた。
卯木氏は、ここでふたつのリストラを断行する。これはそれまでの業界では、当たり前と思っていてもなかなか貫徹できないことであった。
(1) 生産のリストラ
1) 生産の海外移転
生き残りをかけたアイワは、シンガポールへの生産シフトを決断する。
親会社であるソニーはもちろんのこと松下電器、シャープといったライバル企業に比べブランドイメージの劣っていた日本市場での拡販をあきらめたのである。代わって東南アジア・中近東・南米などの途上国市場で、シンガポール製の低価格コンポを武器に攻勢に打って出た。
それまで高価格というイメージがあった日本メーカーの製品に対し、「手の届く価格で買える日本メーカー製のコンポ」というコンセプトが受け、途上国市場で一躍トップブランドに躍進した。
具体的には50ドルを切るヘッドホンステレオ、500ドルを切るミニコンポがその代表格である。
さらに、円高の進行によりライバルの輸出採算が悪化する中、シンガポールから米国、欧州へと輸出エリアのワールドワイド化を図り、先進国市場でもシェアを奪取した。
2) 国内の人員削減
生産の海外移転に伴い、当時国内に三つあった工場をひとつに減らし、3,000人の社員を半年で1,500人へと半減させた。代わりに1974年に進出していたシンガポール工場の規模は2倍にまで広げた。
「為替の安い国で作って、為替の高い国で売れば確実に儲かる。だから日本ではなく、海外の生産を選んだ」(卯木氏)
もちろん、アイワ社内でも少なからず軋轢が生じたことは事実である。しかし、業績が回復し、販売店や消費者から「歓迎」の評価を得ることで、こうした軋轢は次第に解消されていった。
(2) 事業のリストラ
ベータマックス方式のビデオテープレコーダー(VTR)生産からの撤退も、親会社のソニーとの関係を考えれば、思い切った決断である。ここでも「親会社が開発したとはいえ、市場競争の中でVHS方式に敗れた以上、生産にこだわっても仕方がない」という原理原則に従った判断が働いている。
その代わりに、割安な高音質ミニコンポなどの新製品を次々に市場に投入する作戦が展開された。
こうした一連のリストラを推進した卯木氏の原理原則を重視した姿勢と行動力により、就任後わずか3年足らずの1989年3月期決算には営業利益ベースでプラスに回復させた。この「卯木路線」は経営の「行動規範」として後のアイワ高成長の原動力となった。
バブル崩壊後の景気後退により、ミニコンポの値崩れなど国内AV市場が混乱する中、1992年、アイワはシンガポール工場製の低価格ミニコンポ「XG-330」を日本市場に投入した。5万8,000円という他社の半値で発売したこの商品は大ヒットし、それまでの約3倍となる国内シェア20%のトップシェアを獲得した。
しかしながら、その要因は海外生産に象徴される「低価格商品」ということだけでは決してない。アイワ独自の強みがその背景としてあった。
図表2.ミニコンポのシェア
(1)シンガポールでのコンカレントエンジニアリング -他社に先駆けた現地化
アイワの海外生産シフトによる競争力は「安価な労働力」だけではない。マレーシアへの技術移転の例をとっても、シンガポールを中心として設計などの上流工程から量産まで、生産システム全体をできる限り「現地化」を進めてきたことが、好業績につながっている。
1994年時点では日本本社の社員は1,800人弱であるのに対し、シンガポールは1,900人。
「既に人員数では本社を上回っているが、仕事の質の面でも急速に本社に近づきつつある」(アイワシンガポール吉田稔会長兼社長(当時))
また、R&Dセンターの所長はシンガポール人であり、128人のエンジニアの中で日本人は6人にすぎない。
シンガポール、マレーシアの工場で生産される製品の3分の2は現地設計である。同地域が全社の生産高の5割を占めており、按分するとアイワ全体の生産の3分の1近くはシンガポールで設計されていることになる。
生産現場の近くで設計するメリットは、当時新しいモノ作りの手法として注目されていたコンカレント(並列)エンジニアリングの実践にあった。実際、円高以降、日系の部品メーカーの現地進出が相次いでいたため、シンガポール工場の部品現地調達率は95%にまで達していた。こうした効果により、設計期間を半分に短縮することに成功し、素早い部品調達-大量生産のシステムによる低価格化を実現させた。「XG-330」にしても当時の低価格コンポとしては高出力の大型電源を搭載し、大音量でも音が歪まないようにするなどの機能が販売店や消費者に認められたことがヒットにつながった。
(「価格を据え置きつつ、CDチェンジャーやサラウンド再生など、他社に先駆けて新機能を取り入れている。手頃な価格で機能的にも優れることが消費者に評価されている理由」(上新電機商品部長「日経ビジネス」1995年7月17日号))
(2)大手量販店との取組重点化 -コンテナ販売による販売・物流改革
ライバル各社がミニコンポの海外生産を加速する中で、家電量販店の店頭でもアイワ製とデザイン・価格がほぼ同じような商品が並ぶようになる。
「同じ価格なら、機能はまだアイワが上」(家電量販店)という評価はあるものの、割安感は当然のごとく薄れる。実際、「みんなが海外で作れば、生産コストはいずれ横並びになる。これからは、国内の販売コストをいかに下げるかが勝負」(アイワ・川口正夫常務(当時))と認識した上で、次なる競争力の源として、国内の販売・物流システム強化に着手した。
1995年から始まったアイワの物流改革は、1) 拠点量販店政策、2) 配送便数の削減、3) 一括大量配送という3段階にわけて考えられる。
1) 拠点量販店政策 -戦略的な量販店への重点化
商品を大量生産・大量商品に向いた普及品に絞る一方、1980年代末には1万店以上あった国内取引先は、集中販売力のあるコジマなど大手量販店を中心に4,000店にまで絞り込んだ。アイワ関係者はこう語っている。
「まず営業面で、取扱品目が増加している一方で、セールスを増やすわけにはいかず、限られた人員できちんとセールスするには取引先を拠点店中心に選ばざるを得なかった」(家電ビジネス1995年8月号)
もちろん、物流コスト面からみれば、大量配送による物流費削減というメリットがあるが、同社の体力的な要因もあった。
「何よりも、取引の少ない店は配送費を考えると赤字に近いところが多かった。こちらも商売なので、損してまで続けるわけにはいかなかった」(家電ビジネス1995年8月号)
「家電流通は5年後、10年後は否応なく大型店に集約されていくだろうと予測した」(家電ビジネス1995年8月号)
2) 配送便数の削減 -割り切りと交渉術の巧さ
販売先を大型店に集中していく一方、配送便数も少なくした。家電業界では1日1便が一般的であったが、アイワでは週1、2回というところも多い。
「すみからすみまで売ろうとは思わなければいい。小口配送していては物流事情から足が出る。例えば1台の注文であれば、話し合いで採算ラインぎりぎりの5台までというお願いをする」
思い切った割り切りであり、またそれは商売人としては当然の交渉術である。
3) 一括大量配送 -業界初のコンテナ配送のメリット
通常の物流はアイワの宇都宮のターミナルから各商圏のアイワ物流センター-量販センターを通じた各店舗配送である。これに対し、宇都宮ターミナルからの各店配送、コンテナや11トン車で量販センターまで直送している一括大量配送がある。カトーデンキ(現ケーズデンキ)など家電量販チェーン40法人くらいがこの配送方式を採っている。
「余計なサービスは要らないから、その分卸値を安くしてもらいたい」
という販売店側の意向を受けたこの配送方式は大幅なコスト削減につながる。商品別の物流費削減状況は以下の通りである(それぞれ1台あたり)。
- 14型テレビ 10分の1
- ラジカセ 15分の1
しかもこの浮いた分の配送費は販売店に還元し、販売店のアイワロイヤリティを高めている。
「例えばミニコンポの場合、他の家電チェーンとの価格競争が激しいため、世間並みの価格で売れば粗利が2割を切ってしまう。しかしアイワのコンテナ納入のコンポなら粗利を3割近く確保できる」(カトーデンキ飯野常務(当時)・「日経ビジネス」1995年7月17日号)
粗利が1割違うということは、低収益にあえぐ家電量販チェーンにとって、店舗での販売努力が当然変わってくる。カトーデンキのミニコンポの販売台数シェアの5割近くはアイワである。
「浮いた配送費を儲けにしようとは思っていない。この方式では販売店は自社で各店配送をしなければならないので、アイワの商品をうまく売って儲けることで次の販売につなげればいい」(アイワ関係者)
アイワの販促策というような位置づけであろうと思われるが、実際には伝票代や受発注にかかる人件費やコンピュータなどの経費削減ができた。また、国内にある物流センターと全国9カ所の商品センターが不要となるなど、お互いにメリットを享受している。
こうしてアイワは海外シフトでの成功をバックボーンとして、日本市場に再上陸し、独自のシステム構築による「利益を享受できる低価格路線」で成長を続けてきた。
図表3.コンテナ配送システム
おすすめ新着記事

成長市場を探せ 8年連続プラスのスナック菓子、インバウンドも貢献
スナック菓子市場の拡大が止まらない。小売り金額は8年連続プラス、2023年は2桁、24年も2桁に迫る成長で、6,000億円も射程圏内だ。

消費者調査データ シャンプー 首位は「パンテーン」、迫る「ラックス」、再購入意向には高機能ブランド並ぶ
高機能化の流れが続くシャンプー市場。調査結果からは、認知や直近購入などでは「パンテーン」が首位を獲得したが、再購入意向では個性的なブランドが上位に並んだ。

消費者調査データ 印象に残ったもの 働く女性首相誕生の2025年は、万博に沸き、熊と米に揺れた
2025年は女性首相誕生や万博などに沸いたが、、米価高騰、熊被害、異常気象などに揺れた。消費者の印象にのこったのはどんなものだったか。
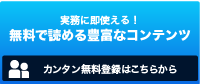
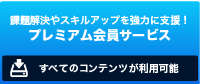
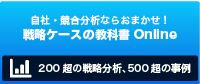


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)




