01
「成長しない」難題
2023年に多くの企業が直面している課題は売上が伸びないことである。経営指標としては売上成長率が低いことだ。この個々の企業の課題を合計すると日本経済の企業サイドの課題でもある。日本経済の過去30年(1992年~2022年)の年平均成長率はわずか0.71%、30年間でわずか110%である。到底、株主が許容できる水準ではない。この結果が、ドル建てでみた場合、他国と比較した際の賃金水準の低さなどの「嘆くべき」事態を招いている。
自国通貨ベースでみると、人口が30年で0.01%しか成長していないことを踏まえると、雇用を維持し、なんとか生産性を拡大してよく頑張っているとも言える。
アベノミクスは、財政政策を拡大して、異次元の金融緩和で政府の財政を担保し、投資環境を生み、民間企業のイノベーションで日本経済を再生する3本柱であった。しかし結局は、財政赤字が拡大し、地価や株価に資本が流れただけであった。加えて副作用として、成長しない経済の富を、地価と株価の上場をうまく活用し、IT関連などで上場した上流層に再配する結果となり、中流層を分解することになった。豊かさの象徴は、郊外戸建ての中流生活から都心高層マンションへと変わった。他方で、既得権益や業界パラダイムに縛られた農林漁業、食品産業、医療介護関連、飲食、宿泊産業、小売サービス産業は、低い生産性の低賃金産業となり、下流の雇用層を形成することになった。
結果として、成長しない富の再配分で凌ぎ、「中流幻想社会」が崩壊したのが21世紀初頭を支配した経済であった。
この経済が変わろうとしている。それは、世界の「21世紀的枠組み」が見え始め、「日本経済の再起動」が迫られているからだ。これを見越して、21世紀の企業存立をかけて、マーケティングをどう組み立てるべきかを考えていくのが本稿である。
参照コンテンツ(階層化の正体)
02
30年ぶりのマーケティング革新の機会
マーケティングは時代とともに変わっていく。2023年という21世紀の初頭に、マーケティングが部分リニューアルではなく全体の構造的革新の必要性を痛感されるのは三つの理由による。この三つは、これまでのマーケティングのパラダイムを変えるものである。
第一は、価値観の転換である。消費に関して、この30年を支配してきた意識は、現在の消費よりも未来の消費を重視するという意識である。購入をもう少し待った方が得をするという判断である。この現在と未来の消費の代替効果が大きいことによって、消費水準が低下した。特に、高齢層でこの効果が大きい。この意識が30年ぶりの値上げによって、現在買う方が得という意識に転換される可能性がでてきた。右肩上がり経済の諸国では、物価が上昇し、所得も増えるので、借金をして海外旅行や大型消費をすることが一般的である。
バブル崩壊から30年、21世紀生まれのアベノミクス世代が10代から20代となり、消費の舞台に登場する。この世代が転換の契機になる可能性を持っている。
第二に、AIの導入によって、消費者と商品サービスを結ぶ接点が大きく変わり、企業の提供技術のイノベーションが起こる可能性がある。
まず、マスメディア、ネットメディアに加えて、AIが情報メディアの一角に入る可能性が高い。マスメディア、ネットメディアは履歴情報をもとに広告収入を事業基盤にしているが、ChatGPTなどのAIは、会員モデルなので広告収入を基盤にしていない。従って、個人情報の履歴を望まない消費者は、選択を相談するメディアとしてAIを利用する可能性が高い。そうなると、既存メディアの利用効果は低下し、新たな接点を模索することになる。
また、ファッション、耐久財などの販売店や専門店、百貨店などの業種では、多くの人材を接客サービスに投入している。職業分類で、「販売・サービス関係職業」が1,605万人で生産人口(約6,300万人)の約26%を占めている。小売や卸・商社などではなく、製造業でも多くの従業員が営業などに従事している。
この領域は、日本の高度な接客サービスを求める社会では重責を担うが、生産性がもっとも低い。消費者の最終接点である販売で、販売員がAIにサポートされたり、AIが補完したり、完全代替したりして、生産性が飛躍的に拡大する可能性がある。消費者も商品サービスの選択にAIを活用して、情報接触が大きく変わる可能性がある。
マスメディアへの広告投下を前提にしてきたブランディングやマーケティングは大きく変わらざるを得ない。
第三は、グローバル市場の分断である。ロシアのウクライナ侵略以後、経済のグローバル化は止まり、世界経済の地域分断化は進まざるを得ない。世界のパワーバランスをみても明らかである。米中対立、ロシアなどの「ならず者国家」が引き起こす紛争、グローバルサウスの台頭などの動きをみれば明らかである。調達機能をグローバル化するコストより、国内及び同盟国での垂直統合するコストの方が低くなっている。その結果、事業の安全性は担保されるが、グローバル市場の販売規模が小さくなり、調達コストが高くなる。つまり、グローバルな「規模の利益」を追求できなくなり、既進出国の文化的独自性や多様性をもとに、「多様性の経済」を享受するメリットが生まれてくる。市場への深掘りによる多様な文化の組合せが新たな可能性を生む。日本製品が海外で受容されて、改めて日本で再発見され価値が認められるという現象はよく見られる。
グローバル市場での「規模の利益」の追求もこれまでのマーケティングを形作ってきたものである。
03
成長できないマーケティング―典型消費財メーカー事例
それでは、これまで成功してきたマーケティングとは何だったのか。ここでこれまでのマーケティングを特定するために【消費財メーカー事例】(図表1)を想定する。
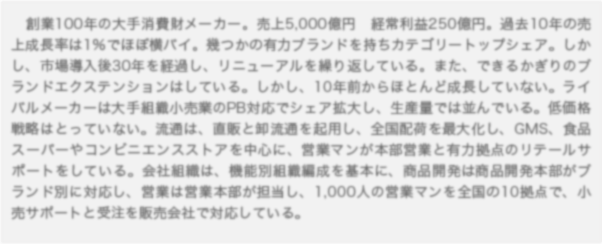
この消費財メーカーのマーケティングは以下のようなものである。
この企業のマーケティングの特徴を機能別に八つで整理してみる。
マーケティングは、ターゲティングから計画する。誰が顧客であり、誰を対象に売るか、である。日本の企業は、オーバーオール(すべて)である。セグメントで分析しても、個々のセグメントをターゲティング(標的)にすることはない。行き過ぎた平等の信念が貫かれている。販売しているのは、モノであり、モノの属性であり、機能である。それが顧客のニーズを満たすのであって、補完製品、情報コンテンツやサービスは重視しない。価格はよいものを量産してできるだけ安くして競争優位を築く。ブランドは認知率であって、他社を圧倒するプロモーションで顧客の指名を獲得する。流通は、配荷率をフルにするためにあらゆる業種業態小売に開放し、直販と卸でフォローする。営業は地域ごとに攻撃力でライバルを上回る。
この会社の八つの機能を特徴づけた。それぞれが機能固有の特徴を持ち、競争優位に繋がっている。さらに、個々の機能が他の機能との依存、補完、相乗して、より強い競争優位に繋がっている。
04
市場支配的マーケティングの強み
全体としてみるならば、製造でコスト優位を確保し、シェア拡大のための量的優位のマーケティングである。研究開発で技術差異を生み、それを製品化し、ブランディングして商品改良を繰り返して市場を深耕する。
自社の技術で、他社が真似できない差異が明確な原料や機能をベースに商品開発を行い、覚えやすさなどでネーミングやパッケージングをし、中流家庭に受け入れやすくする。そして、大量のマス広告でブランドネームの認知率を最大化し、サンプリングなどの量的プロモーションで地域シェアトップをとる。
このような展開は、できるだけ消費者からの指名買いを高める「空中戦」のプル・マーケティングである。もう一方で、営業は、全国の小売店配荷率を最大化するために、卸を起用し、拠点店に対しては自社営業マンの攻撃力を活かして売場を確保していく。いわば、プッシュの地上戦のマーケティングである。このように宣伝広告費や営業マンの量的優位のうえで、ライバルよりも高いシェアを獲得し、奪っていく仕組みである。
個々の機能が強いだけでなく、機能が他の機能と密接につながり、新たな強みを形成していることがわかる。技術優位を活かす機能差別化、機能差別化を浸透させるネーミングと、認知率を狙うマス宣伝、マス宣伝の基盤となる全国配荷、全国配荷のための過剰な店舗数獲得とそれを支える量的営業体制など、それぞれの機能が補完関係にあって、全体の強みを形成していく。ライバルからみれば、ひとつの機能で優位にたつことができても全体では勝てないのでシェアは奪えない。
業界の違いはあるが、1990-2000年代の花王、資生堂、パナソニック、味の素、アサヒビールなどの消費財大手は他社には真似のできない仕組みを持っていた。
アメリカ生まれのマーケティングに独自の流通-営業の仕組みを取り込んだ「日本的マーケティング」であり、ひと言で言うなら「市場支配的マーケティング」である(図表2)。

さらに、市場支配的マーケティングは「日本的経営」の本質でもあった。特に、小売を系列化する政策は、「系列化」が参入障壁になっているという理由で、「日米構造協議」で課題となったほどだ。
この日本の土壌で完成したマーケティングは、佐川幸三郎氏(元花王会長)の「新しいマーケティングの実際」(プレジデント社)に実務的に体系的に整理されている。
>> 次へ