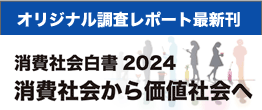製品ラインのランクに応じて多段階な価格設定をするもので、この価格ランクをプライス・ラインや価格線ということから、価格ライン政策とも呼ばれます。例えば、ネクタイなどで見られる、3,000円均一、5,000円均一、一万円均一などが典型例で、普及品・中級品・高級品といったランクを設定し、そのランクに応じて同一価格を設定する方法です。
プライス・ライニングは、多品種の製品を販売していて、個々の製品について個別に価格設定をするのではなく、製品ライン全体で利益最大化を狙う価格設定をする場合に用いられます。
消費者にとっては、いくつかの価格ランクに分かれていると、自分自身の価値判断と合致した価格帯の製品を容易に選択できる一方、逆に、実勢価格がよく分からない場合は、選択が難しくなることもあります。
プライス・ライニングという視点に立つと、顧客の購買力の格差(ランク)を想定した製品ラインを構築するという切り口が得られます。特に、機能や性能など分かりやすい製品属性によるバリエーション化が可能な場合、様々なバリエーションを同一価格に設定するのではなく、顧客の購買力ランクに適合させたいくつかの価格帯で設定することで、これまでと異なる製品体系を開発することができます。例えば、自動車では同一車種でも多数のグレードが準備されています。
一方、企業としては、高い価格帯を設けることで普及品の安さを訴求したり、安い価格帯をラインナップすることで、高い価格帯の製品の高級感を打ち出すことができます。ただし、設定するそれぞれの各価格帯は、その価格帯における機能や性能、品質、グレードなどを代表するものとなるため、消費者が明確に品質差が認識できるだけの価格差になるよう工夫する必要があります。
無料の会員登録をするだけで、
最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。
参照コンテンツ
関連用語
- マーケティング用語集 スキミングプライス
- マーケティング用語集 ペネトレイティングプライス
- マーケティング用語集 オープンプライス
- マーケティング用語集 プライスリーダー
- マーケティング用語集 製品ラインにおける価格設定
- マーケティング用語集 需要の価格弾力性
おすすめ新着記事

成長市場を探せ ビスケット市場、4年連続プラスで初の4,000億超えに(2024年)
緩やかに増減を繰り返してきたビスケット市場が伸びている。2020年から4年連続プラスで、2023年はついに4,000億円を超えた。コロナ下でも堅調な動きを見せ、2023年の販売金額は4,260億円で、コロナ前の2019年比で1.13倍となった。

消費者調査データ ノンアルコール飲料 首位は「ドライゼロ」、追う「オールフリー」「のんある気分」
2022年のノンアルコール飲料市場は8年連続で拡大を続け、過去最高と推定される。調査結果をみると、ビールテイストの「アサヒ ドライゼロ」が、全項目で首位を獲得したが、再購入意向ではカクテルテイストやワインテイストなどのブランドも上位に複数ランクイン、ノンアルコール飲料の幅の広がりを示している。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター 20代男性の内食志向にマッチして伸びる冷凍餃子
数ある冷凍食品の中で圧倒的1位の生産量を誇る冷凍餃子は誰がなぜどのように購入しているのか調べてみた。餃子の選好度、購入頻度、購入増減とも20代が他の年代に比べて高く、冷凍餃子は若い年代が牽引して、拡大してきていることがわかった。


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)